週末土日は、某所でBasic Course 2024 第3回、第4回が行われた。
今回のテーマは根管治療実習。

以下のようなプレゼンをまず行い、実習へと移行した。
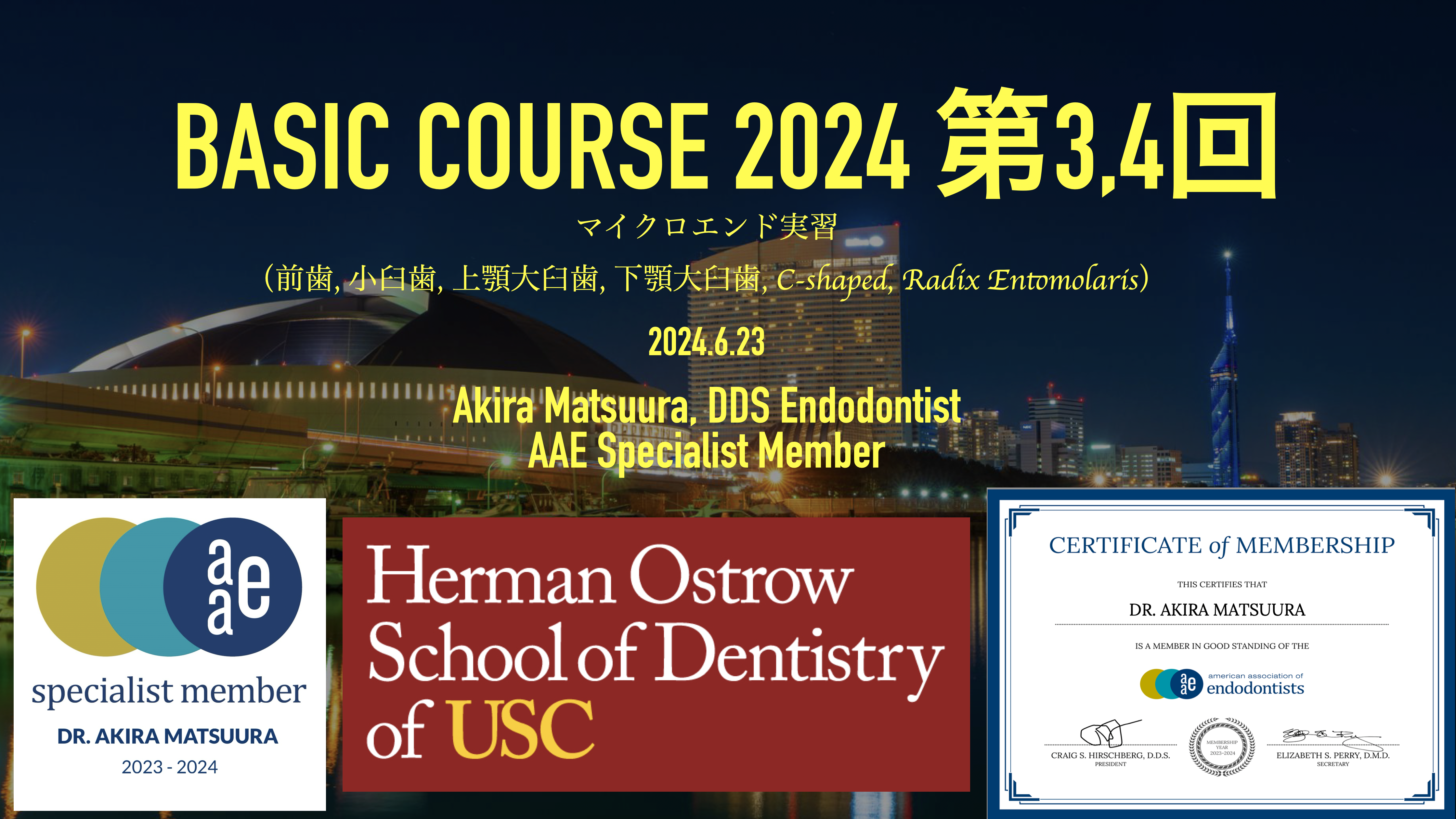
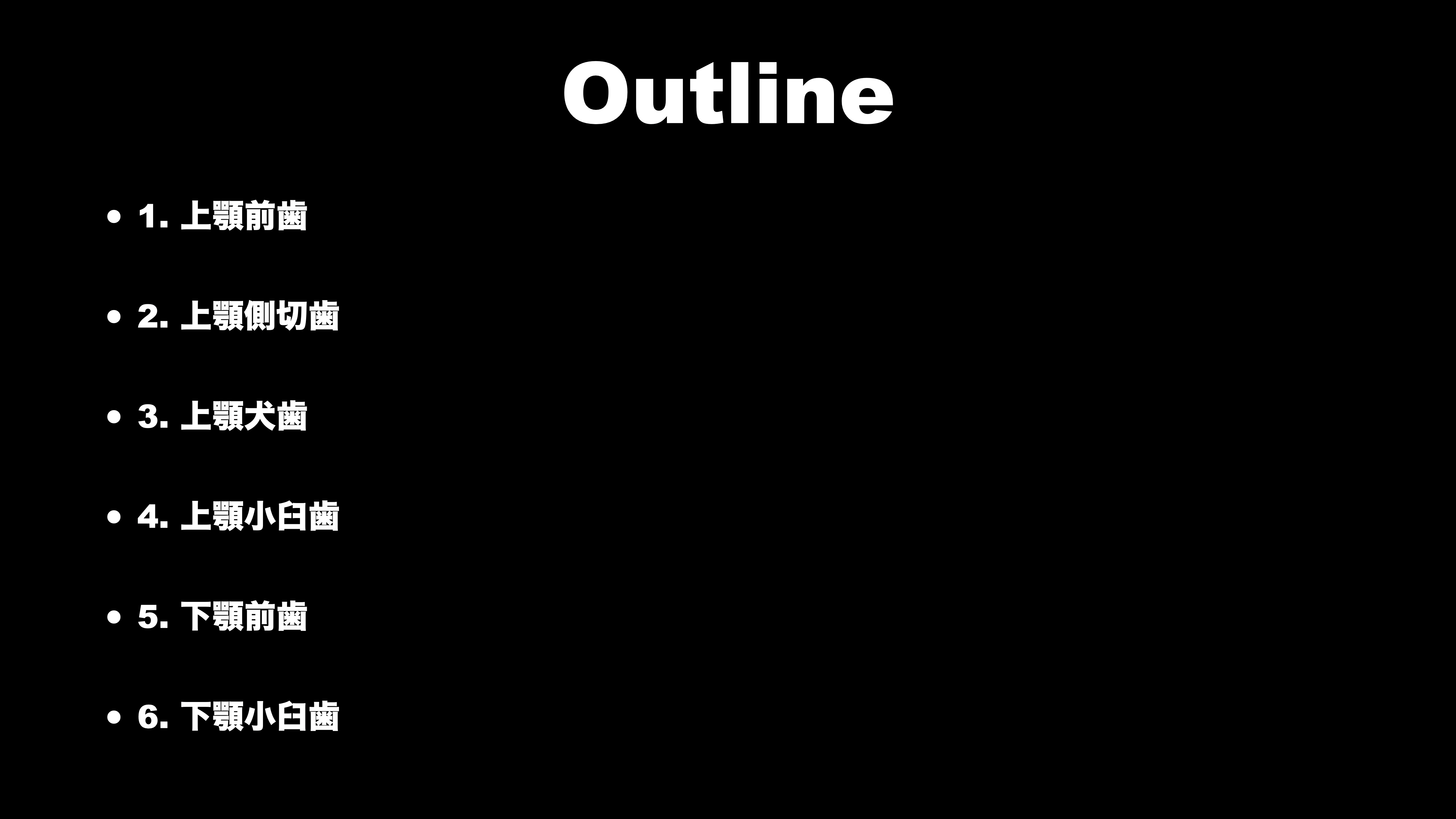
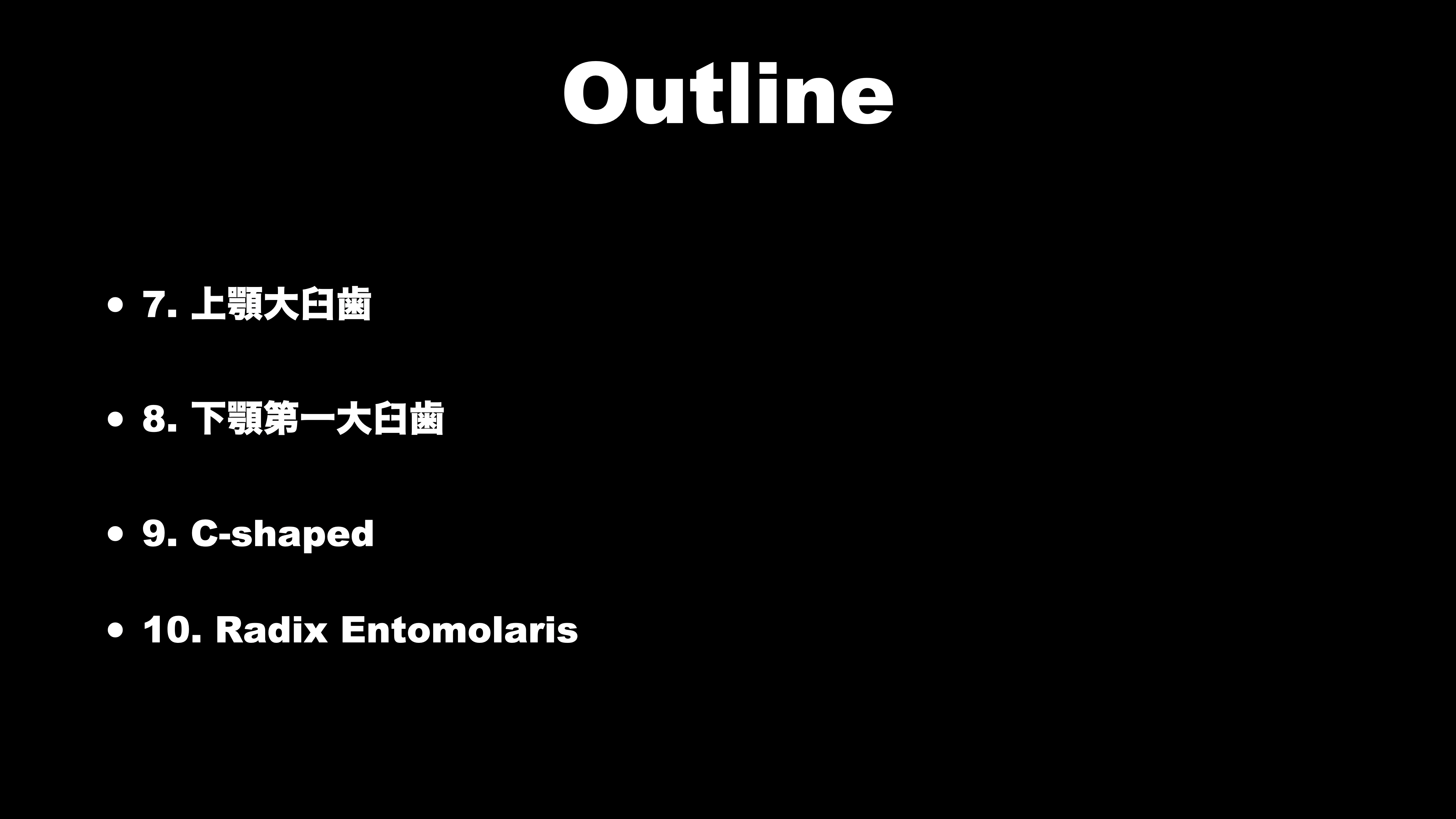
今回は今まで講義であまり扱わなかった、樋状根について詳細を説明した。
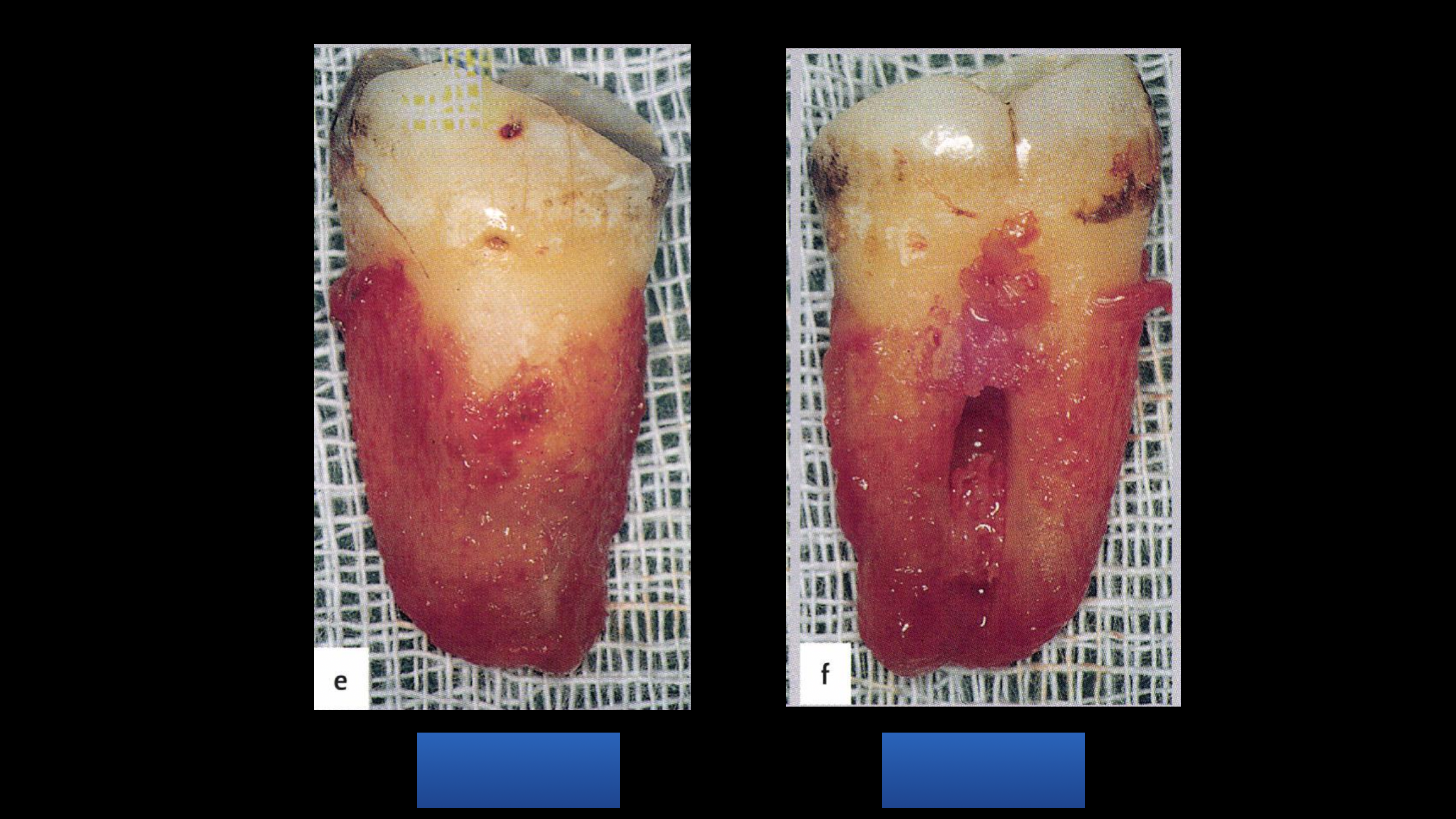

上記の絵を見て、どこが近心で、遠心で、頬側で、舌側か?わかるだろうか?
わかるようにしましょう。
そして、この下のPAが意味することは何だっただろうか?
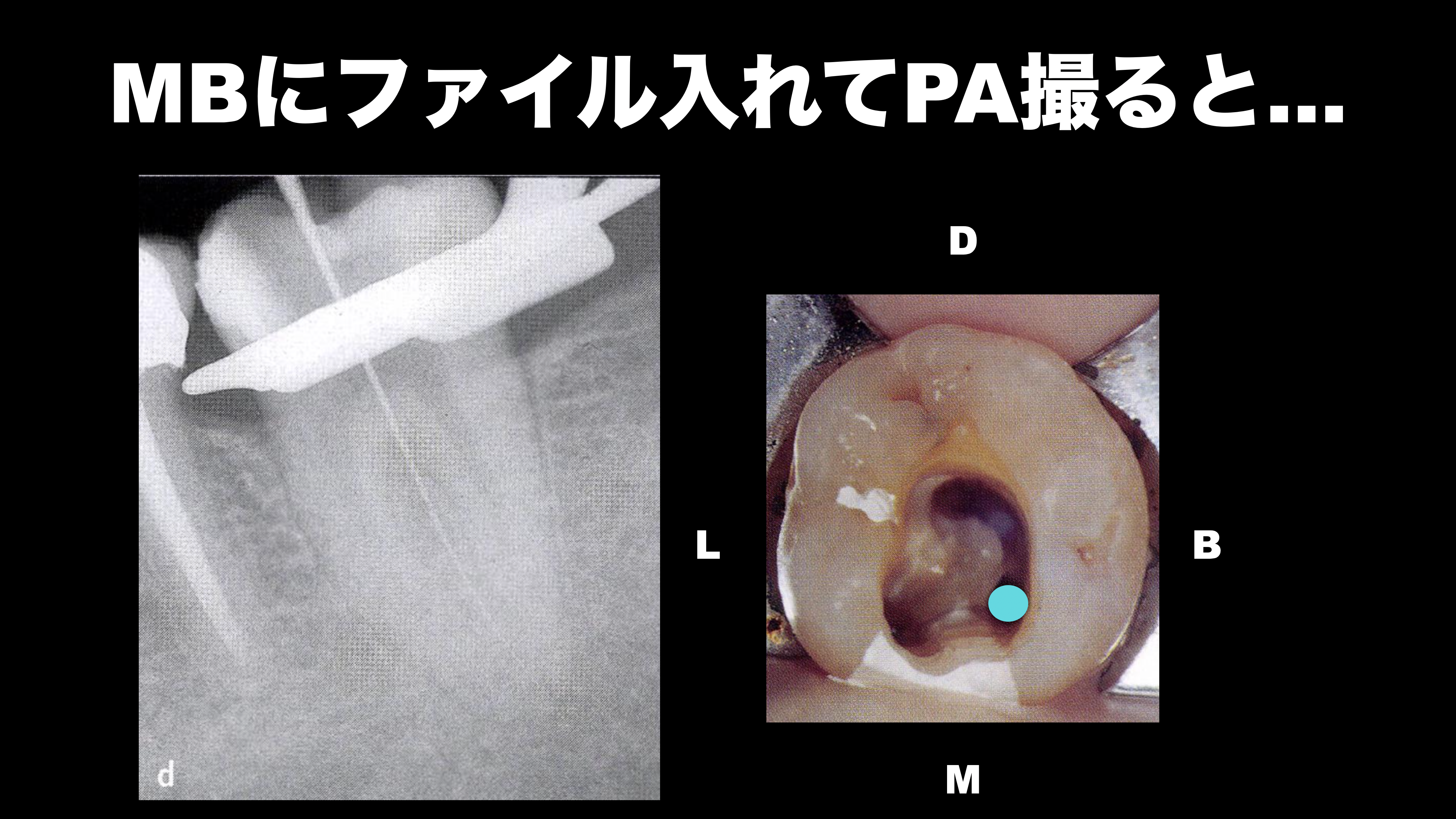
穿孔?していただろうか??
結論は以下だ。
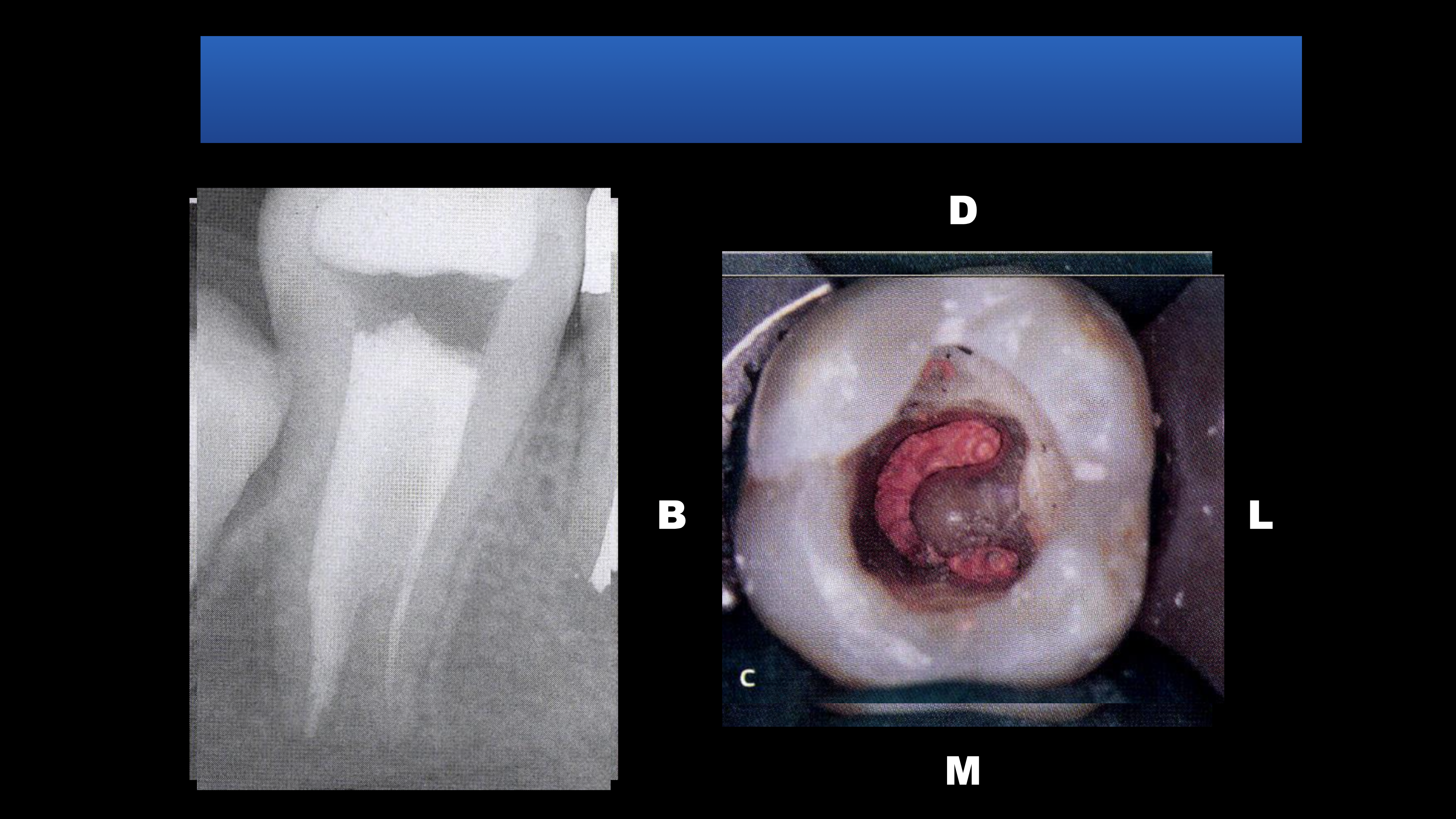
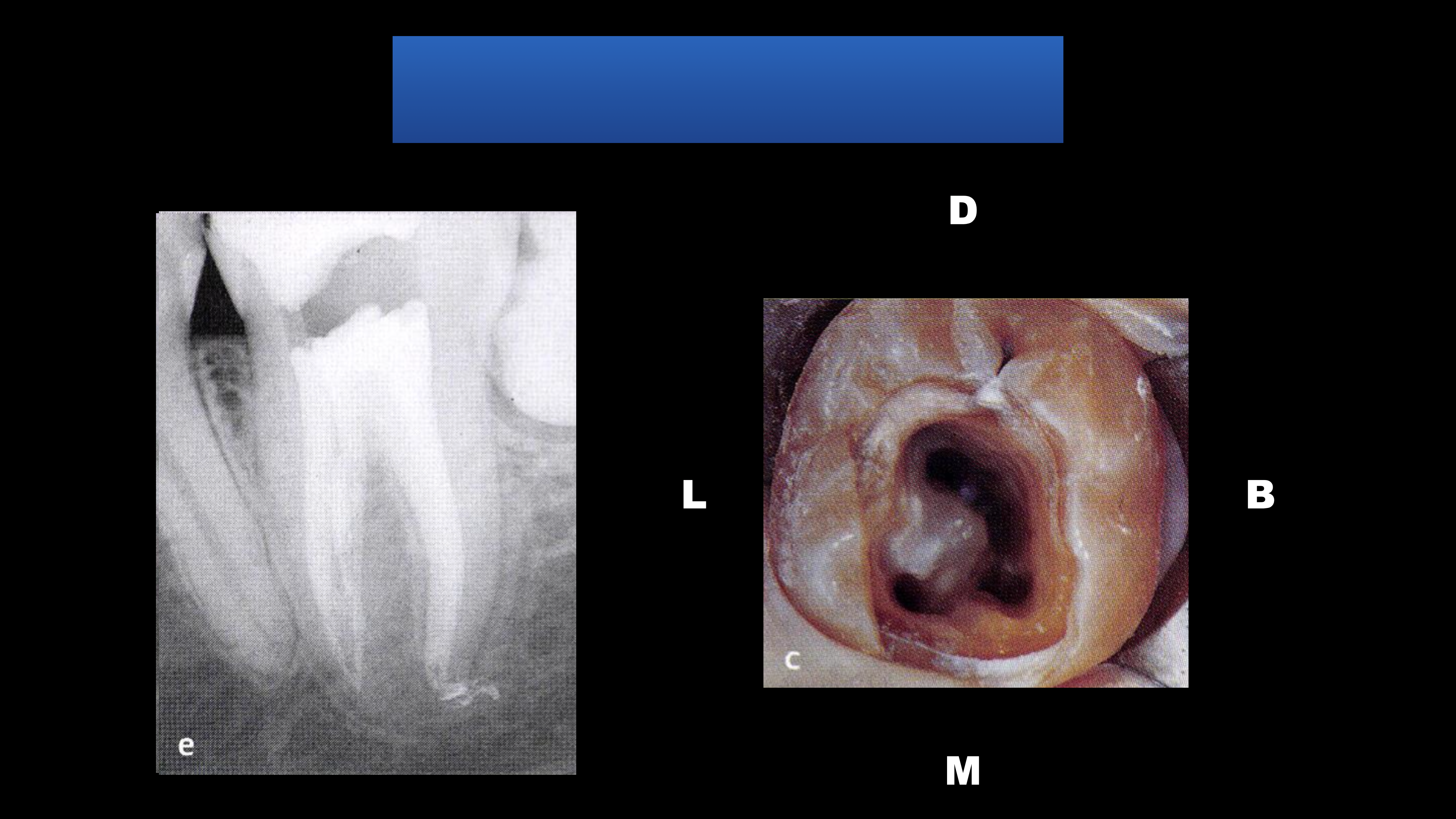
どこの根管がどこの根管に合流することが多かったか?を復習しましょう。
とはいえ、大臼歯をGPに根管治療させること自体がアメリカでは異常なことではあるが。。。
そして某社とともに開発した?Radix Entomolaris模型を使用して、Radixの形成について説明した。
通法と変える必要がある。
なぜか?ファイルに負担がかかるからだ。
そして、
プラスチック模型の方が、レッジやトランスポーテーションが起きやすく難しい。
ほとんどの受講者が撃沈していた。
その点でも、インド人の歯牙の方が一日の長がある。
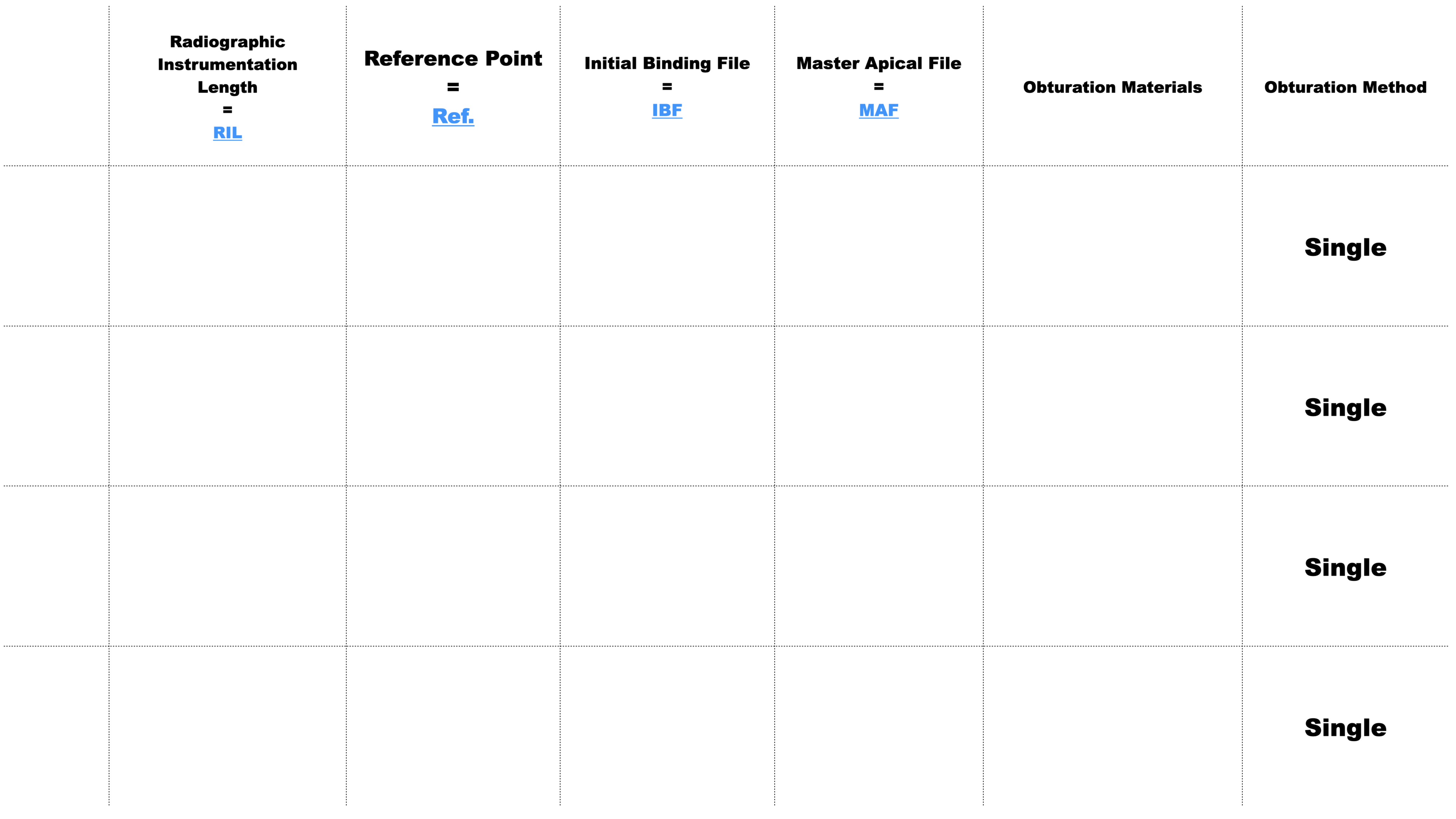
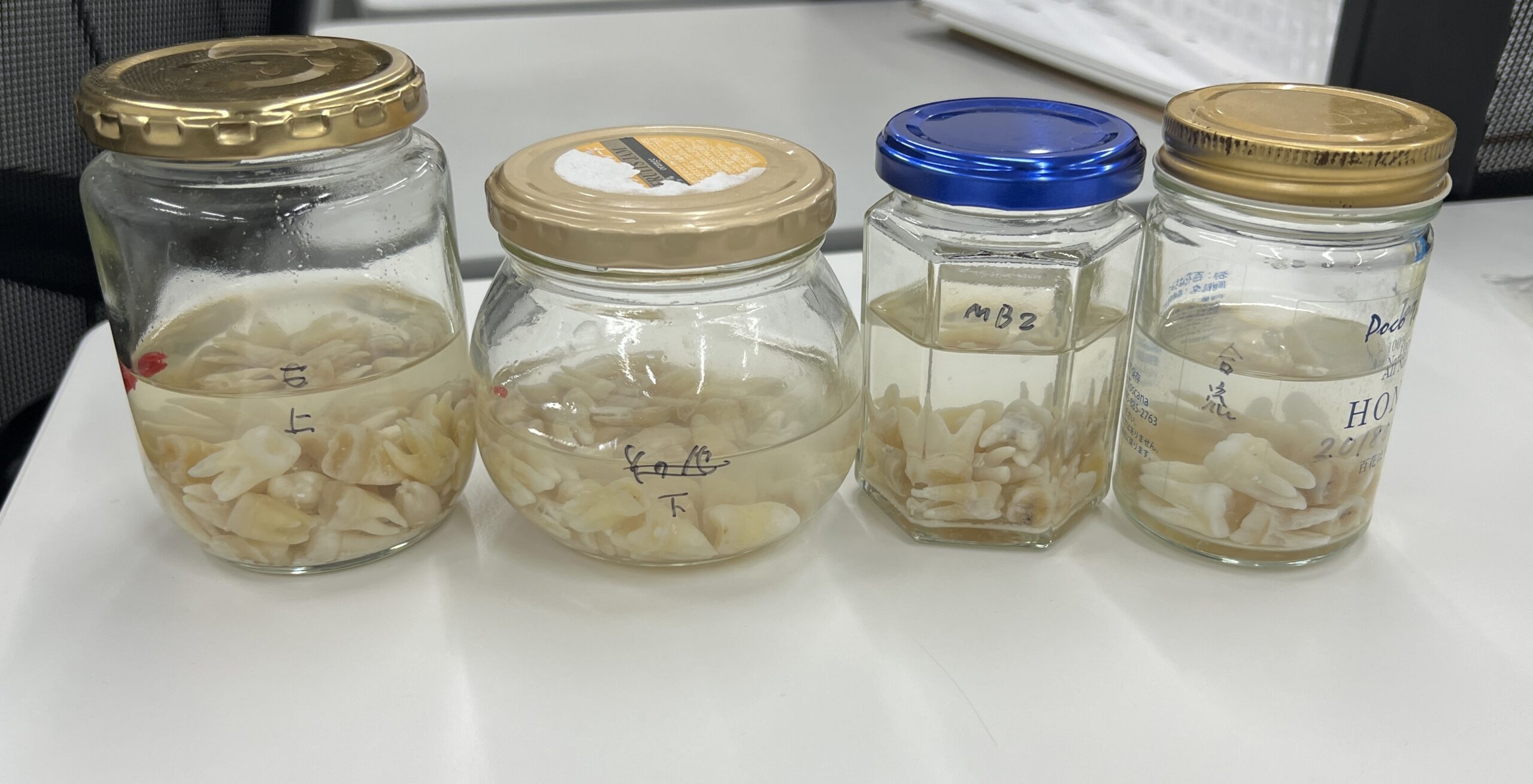
歯牙は、
bforbones
で購入できる。

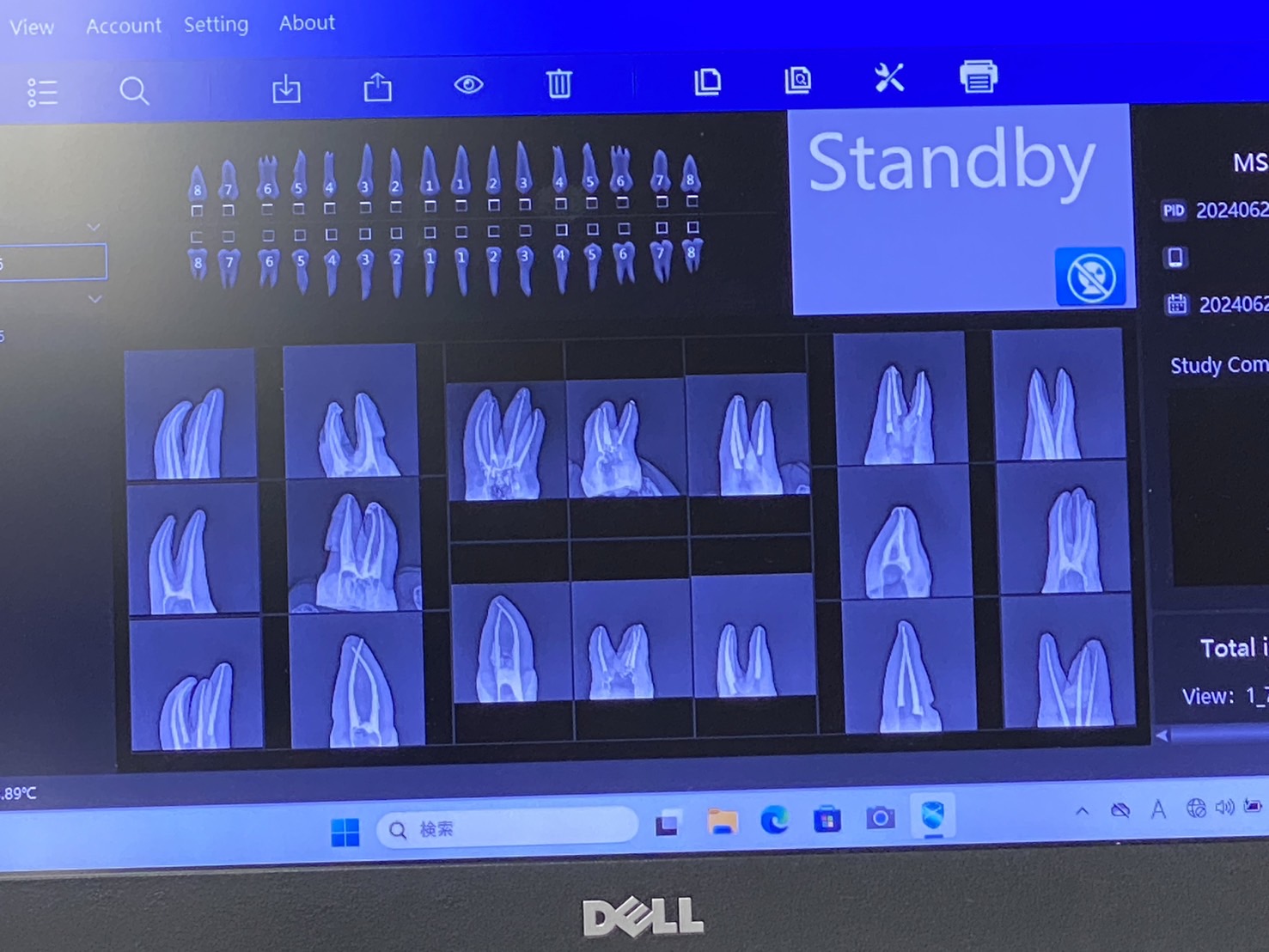
どの根管がどの根管と合流するか?を予測してやるには、術前の予備知識(解剖学的知識)と2枚のPAだけではなく、CBCTを撮影が必須になる。
次回の実習(テスト)では、CBCTを撮影して実習に臨んでもらいたい。
そして、実習に使用するものは全て準備して来てください。
2日間、お疲れ様でした。
