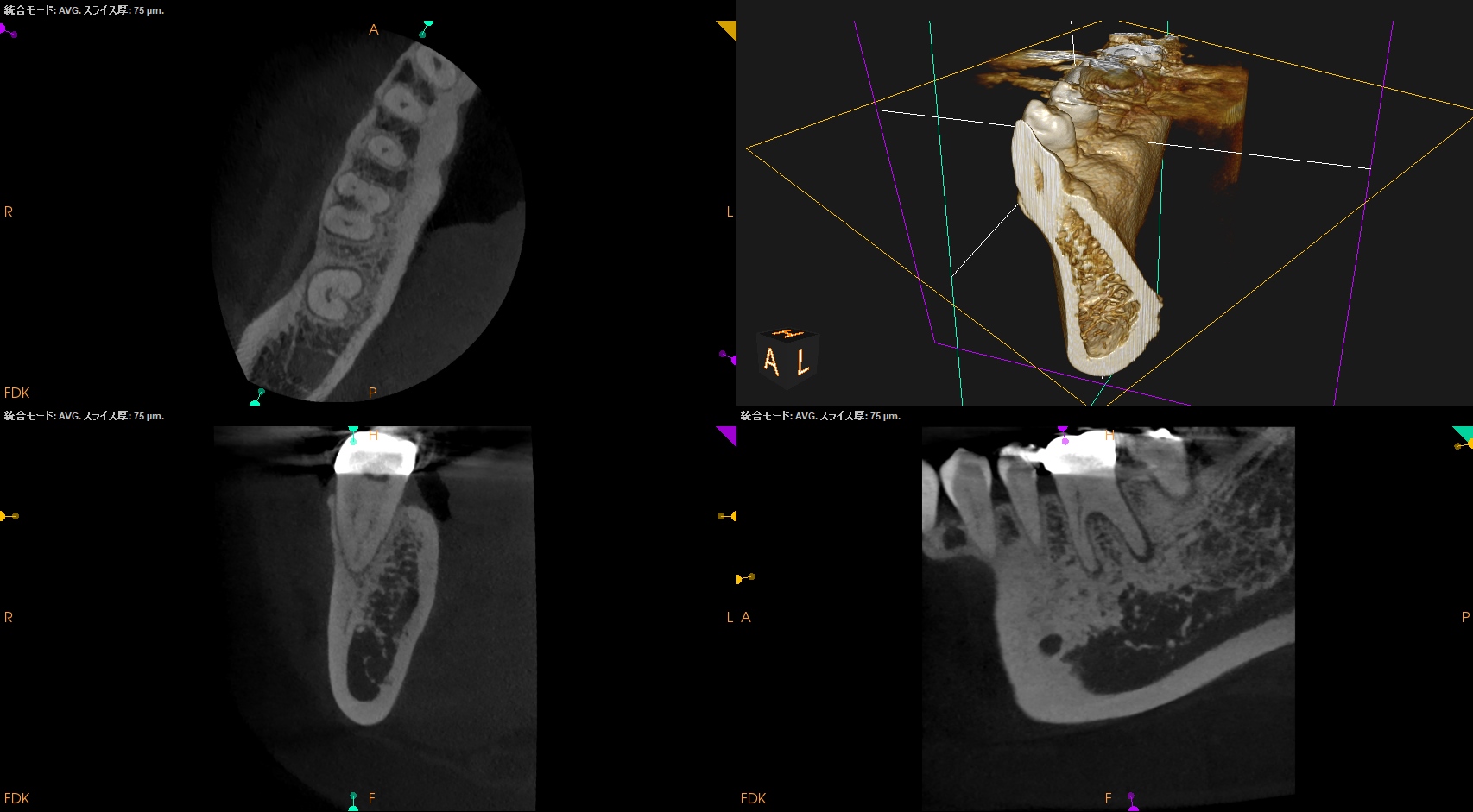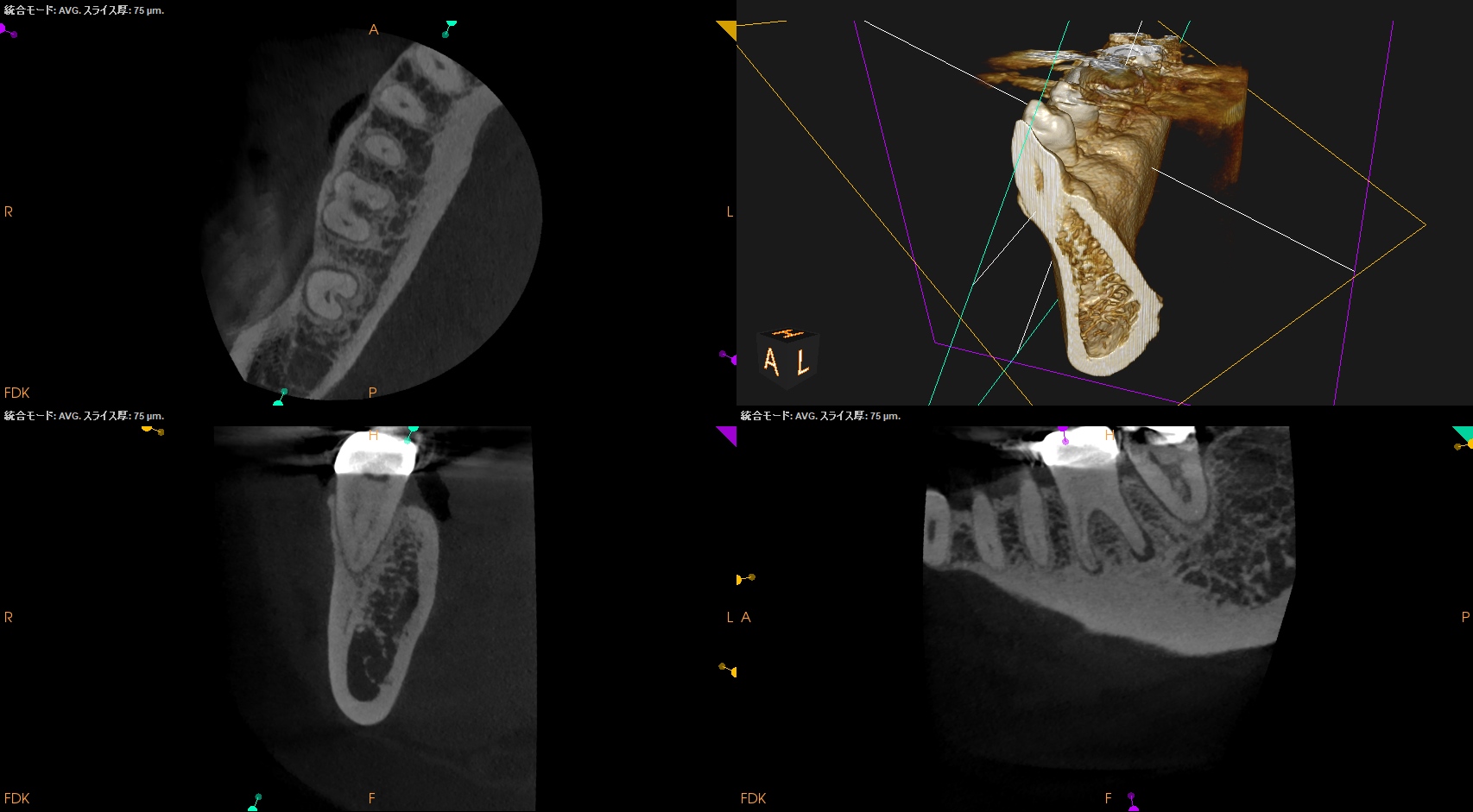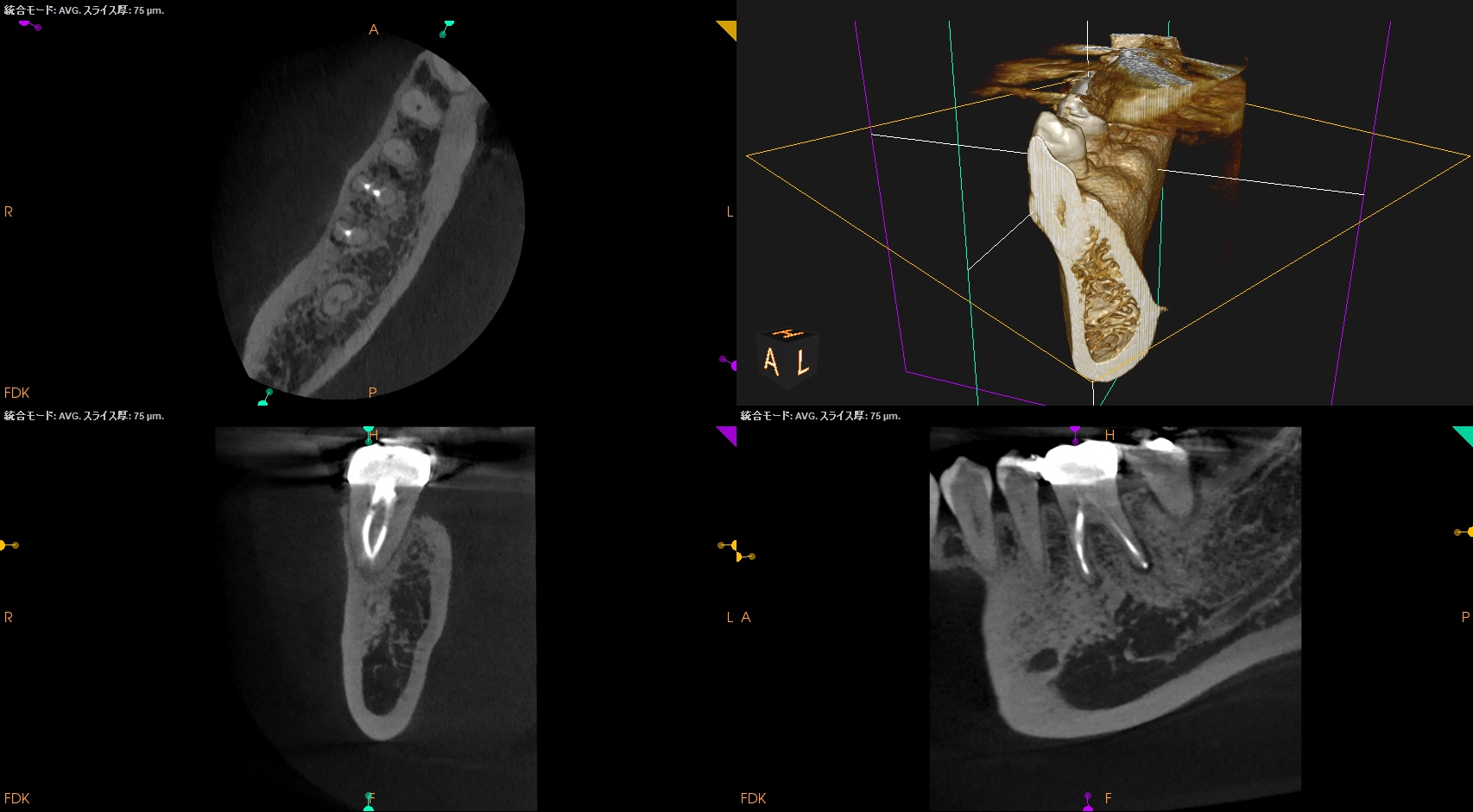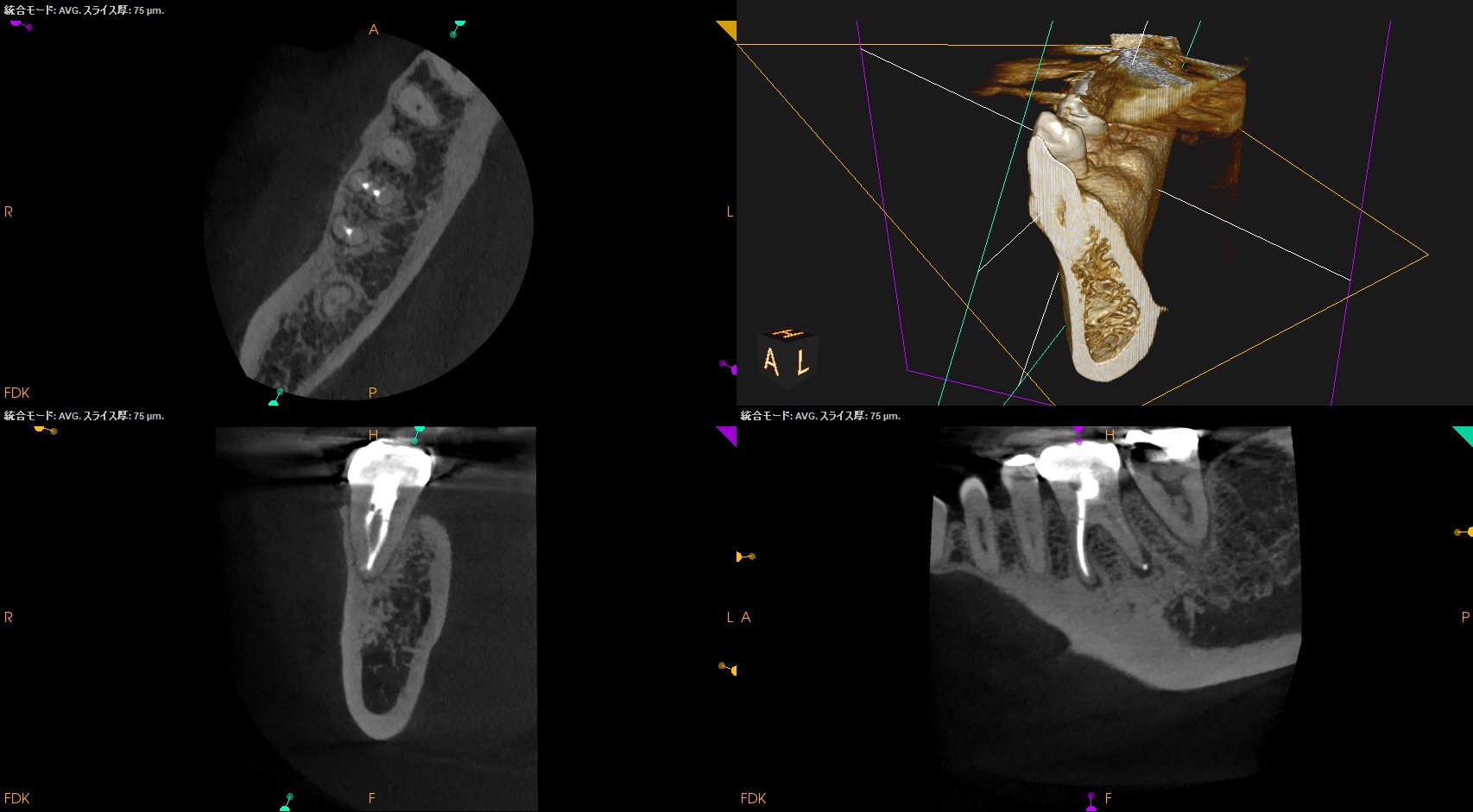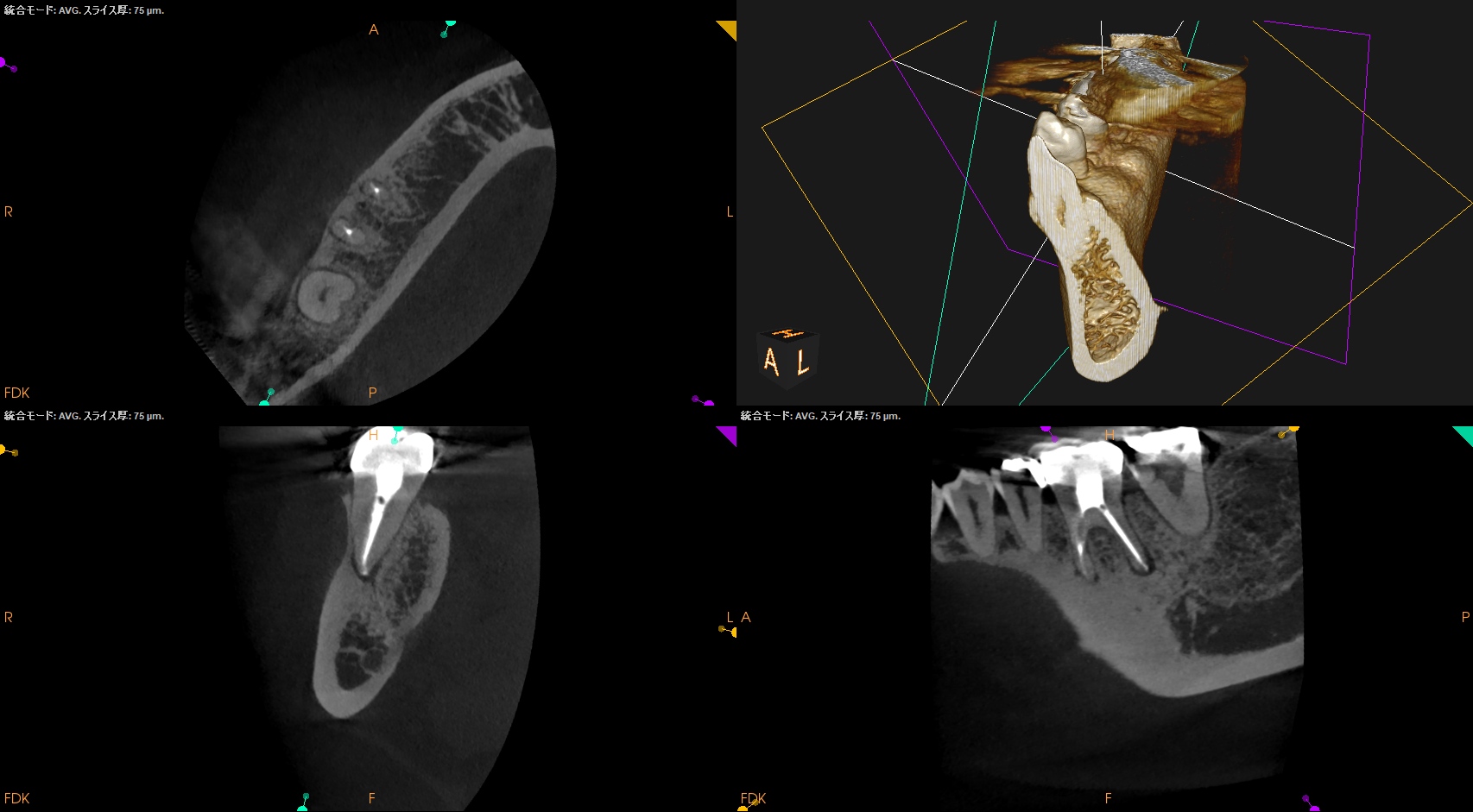紹介患者さんの治療。
主訴は、
右下奥歯の咬合痛。歯にひびく感じがある…
である。
歯内療法学的診断(2024.10.8)
#30 Cold NR/20, Perc.(+), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)
#31 Cold+2/2, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)
主訴は紹介状通りオールセラミッククラウンで補綴された#30だろう。
PA, CBCTを撮影した。
PA(2024.10.8)

M, Dの根尖部に病変が認められる。
が、判然としない。
特に、患者さんに対しては、だ。
CBCT(2024.10.8)
MB
ML
MLが直線的根管でMBがそれに合流していることがよくわかる。
このように、
ヨシダのトロフィーパン スマート オシリス3D
まあ何のことかわからないが、
要はアメリカのCarestreatm社のCBCTの画像の鮮明さ、その使用しやすさは他者の追従を許さないだろう。
が、断っておくが、私はヨシダのスピーカーではない。
さておき、この画像から言えることは、この症例はML主根管でMBはそれに合流しているという事実である。
治療は容易だろう。
D
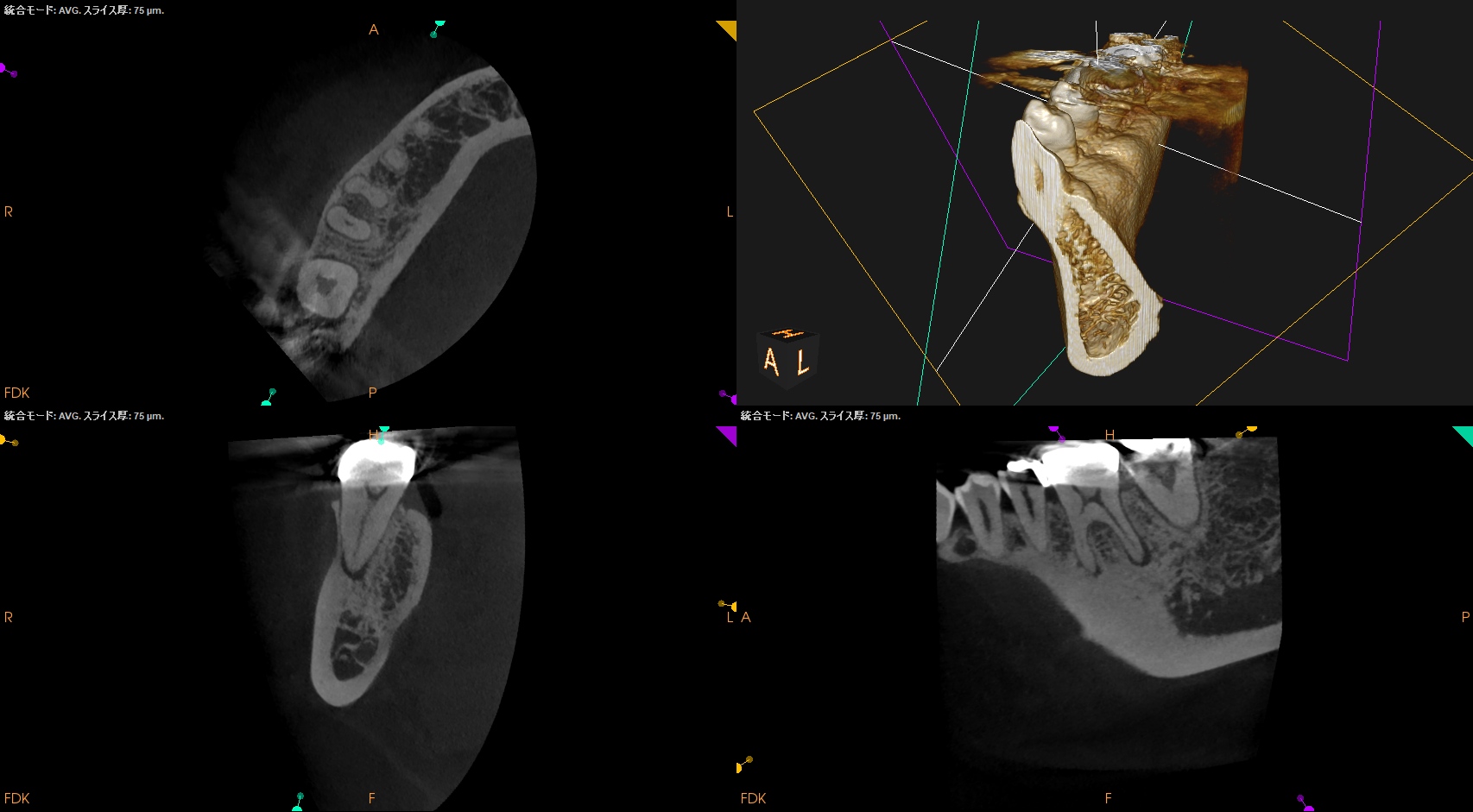
遠心根は1根管だ。
そして根尖病変があるのでここは穿通必須だろう。
以上を整理するとこの歯の治療は、
1. 2根管が合流する小臼歯の根管治療
と
2. 前歯の1根管の根管治療
の合体であると言える。
これは、30分程度で治療が終わる案件だ。
歯内療法学的診断(2024.10.8)
Pulp Dx; Pulp Necrosis
Periapical Dx; Symptomatic apical periodontitis
Recommended Tx; RCT
ということで、別日に根管治療へ移行した。
☆この後、治療動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。
#30 RCT+Core build up(2024.10.9)
生活歯を形成して、根管が石灰化していることがよくわかるだろう。
そして失活するとこのような悲劇?を生むのである。
そして、動画の最後にしたことが理解できただろうか?
短針で遠心根を
スカウティング
している。
スカウト?野球じゃないだろう!というあなた。
あなたはそれではこの業界では素人だ。
遠心根をスカウティングしたのちに、ProTaper SXを根管へ挿入した。
D, MLと形成し、Dから作業長を測定するものの、C+ #10,8,6が穿通しない。
こうなれば、機械的な穿通だ。
CBCTを参考に作業長を目測する。
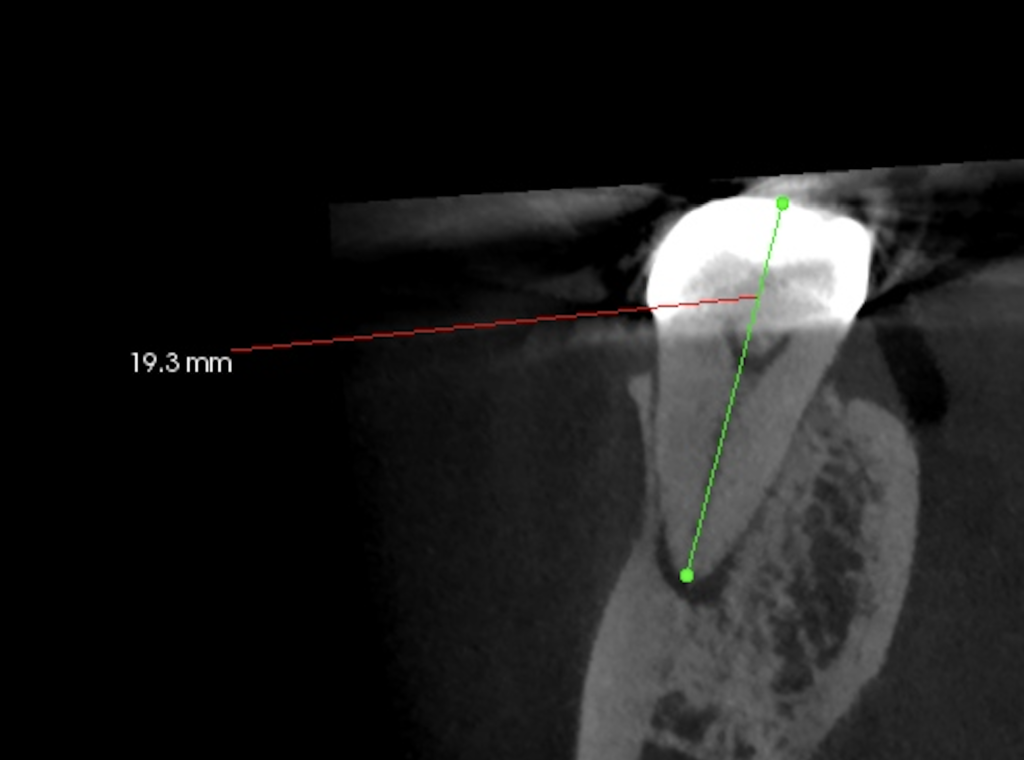
19.3mmあるので、20mm根管を突くことにした。
ラバーストップまで形成できた。
ということは穿通したのだろう。
作業長を測定すると、Apexまでファイルが挿入できた。
MLはC+ File #10で問題なく穿通できた。
それぞれ、#40.04まで形成する。
そして、MBだ。
MLに#35.04のGutta Percha Pointを挿入し、MBにC+ファイルを入れると以下のようになった。

これでメインの根管のMLの作業長が19.0mmで、
そこに合流するMBの根管の作業長が17.0mmとわかる
だろう。
これを術前に予測して治療へ移行することが重要なのである
ということをここでも強調しておこう。
ということで作業長等は以下である。
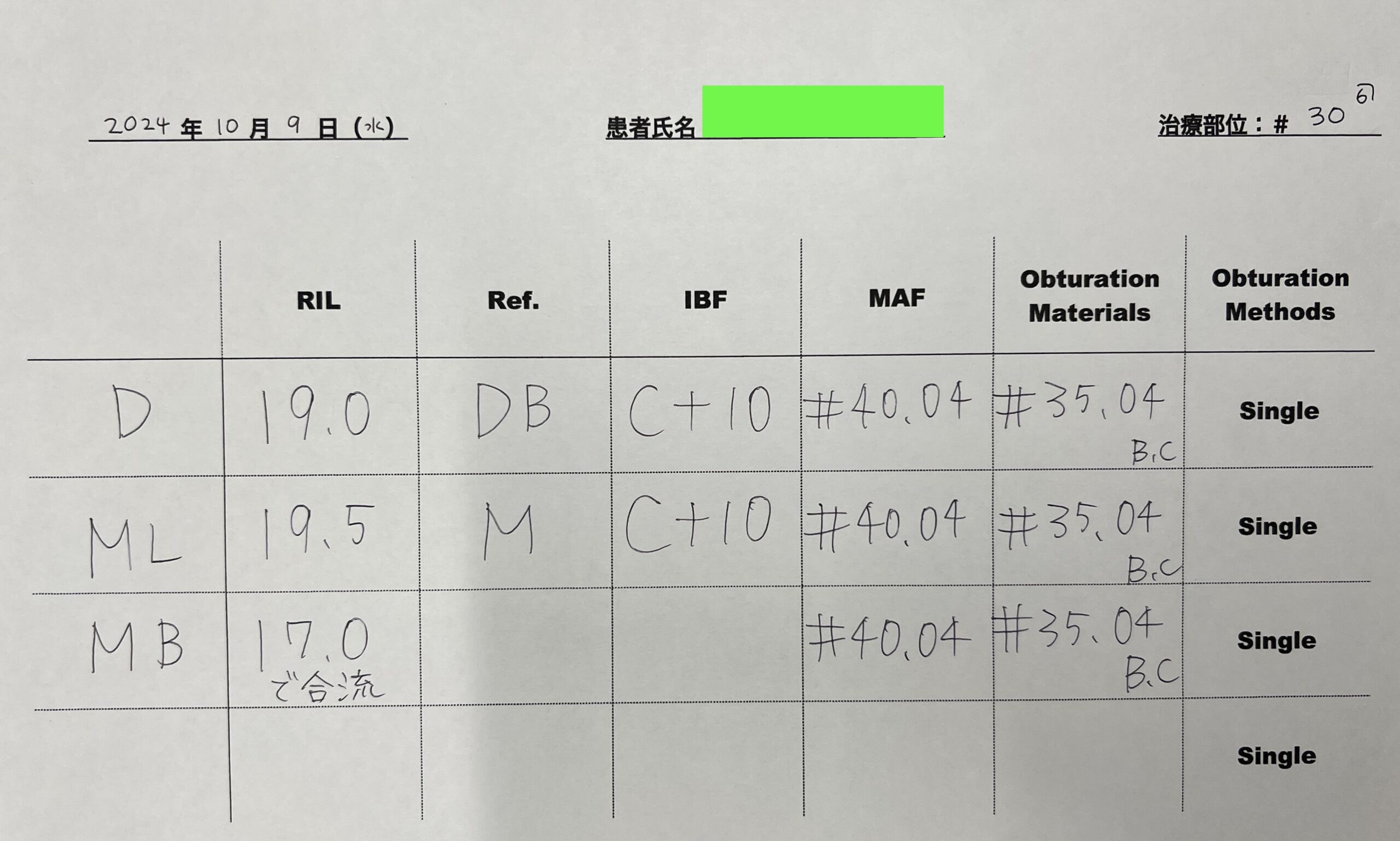
術後にPA, CBCTを撮影した。(ちなみに治療は30分で終了している。)

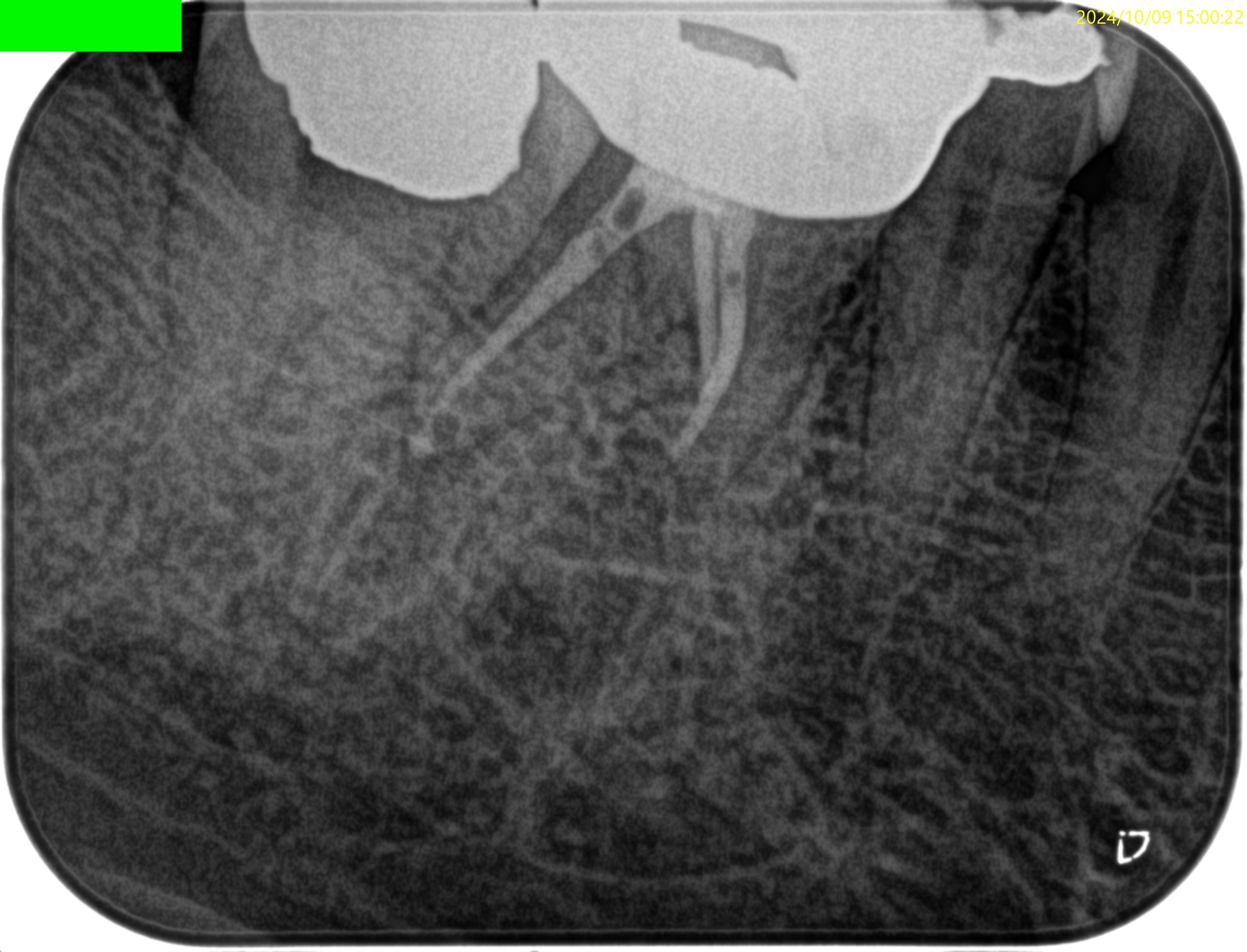
MB
ML
D
問題はないだろう。
繰り返すが、このケースで重要なポイントは、
MLが主根管でMBがそれに合流しているというのを術前に把握し、それを臨床で機械的に実行できる能力があること
である。
それに、
どこの歯科大学を出ているとか、海外の大学院を出ているか?いないか?など何の関係もない。
その能力は、
個人の努力でどうにでもなる
からだ。
が、個人の努力には限界があることはお分かりのとおりだ。
それを埋めるには、専門家に教わるのが最短の道であることは論を俟たない。
ということで、
Basic Course 2025
への多くの先生の参加をお待ちしています。
ということで、次回は1年後である。
また、その経過をお伝えしたい。