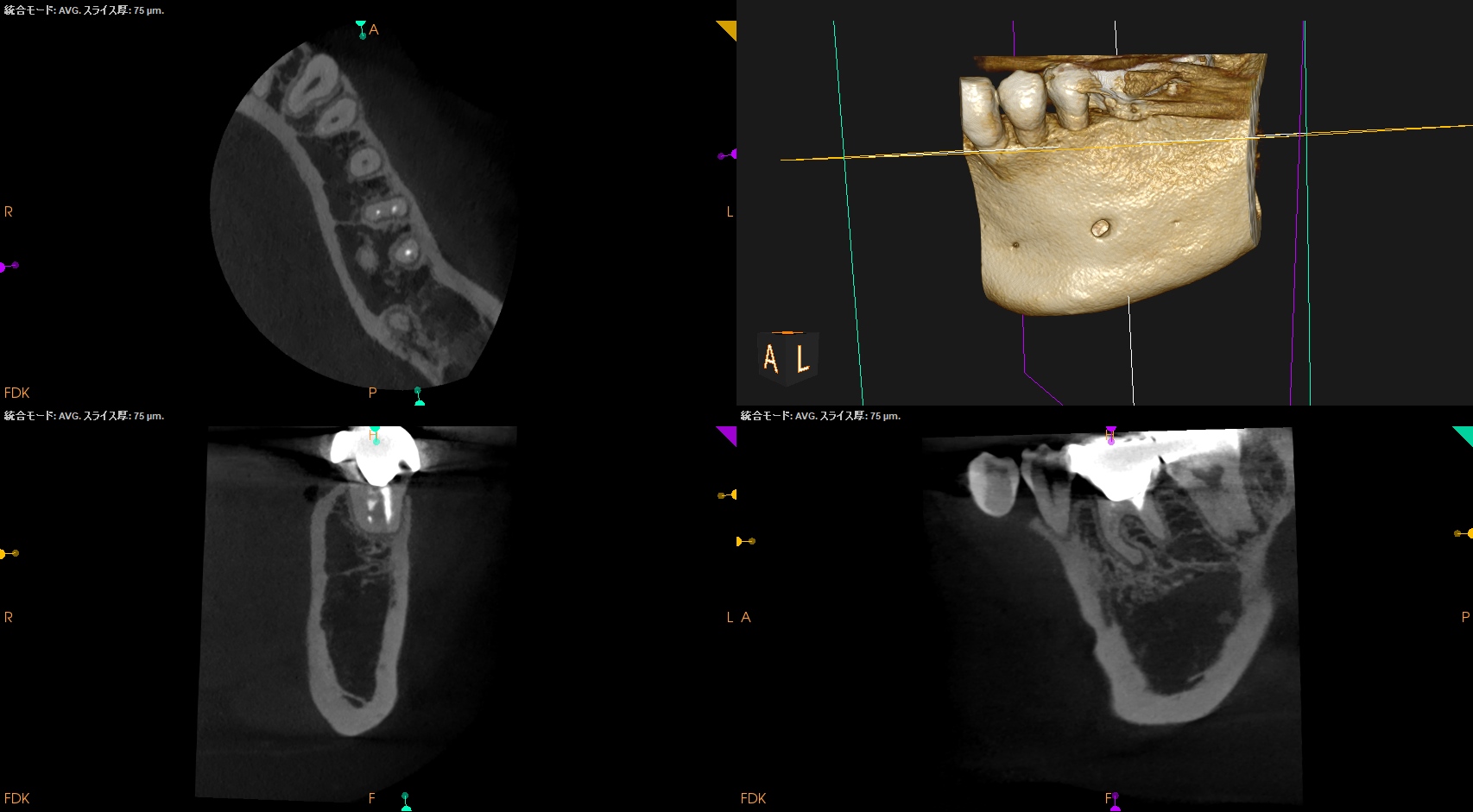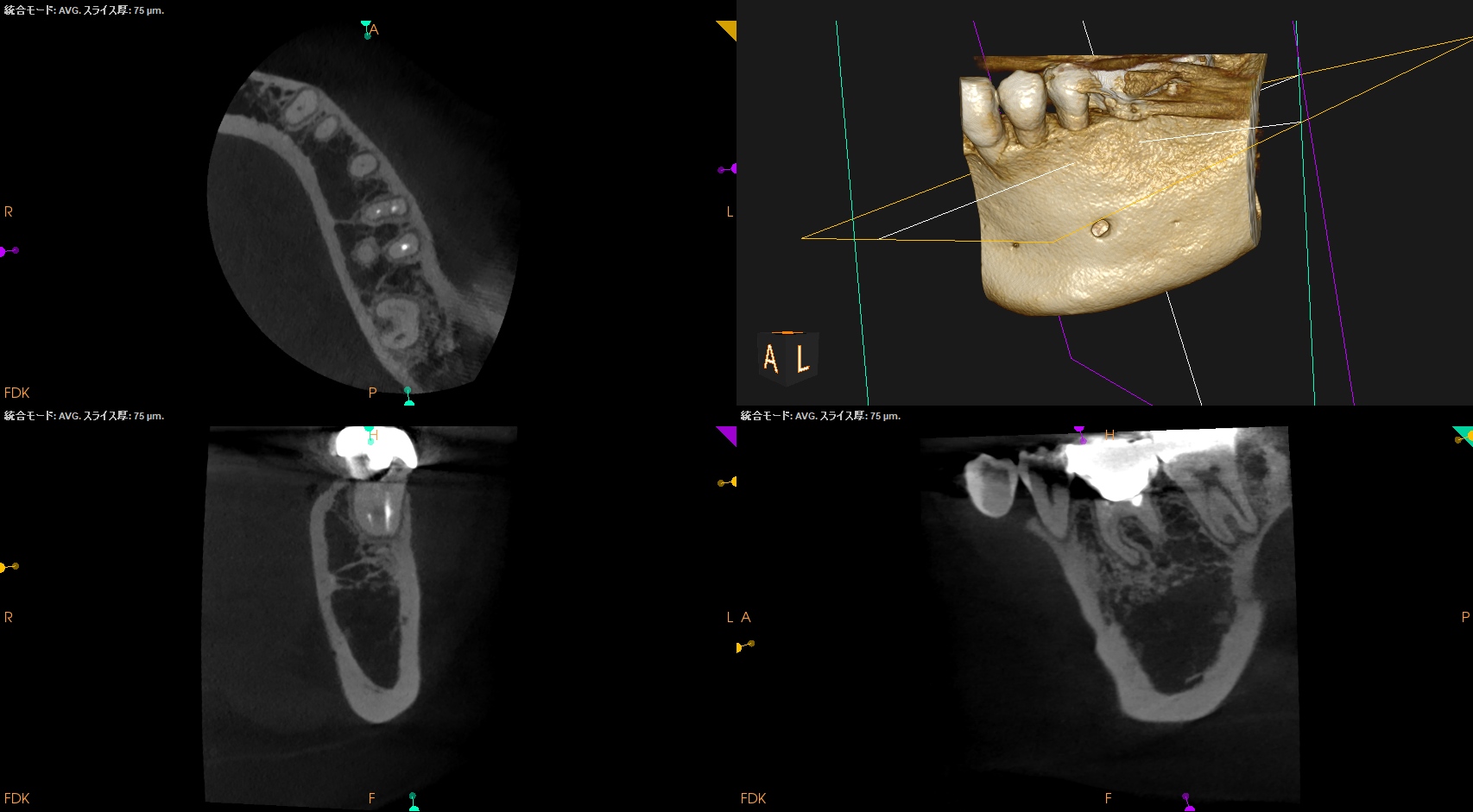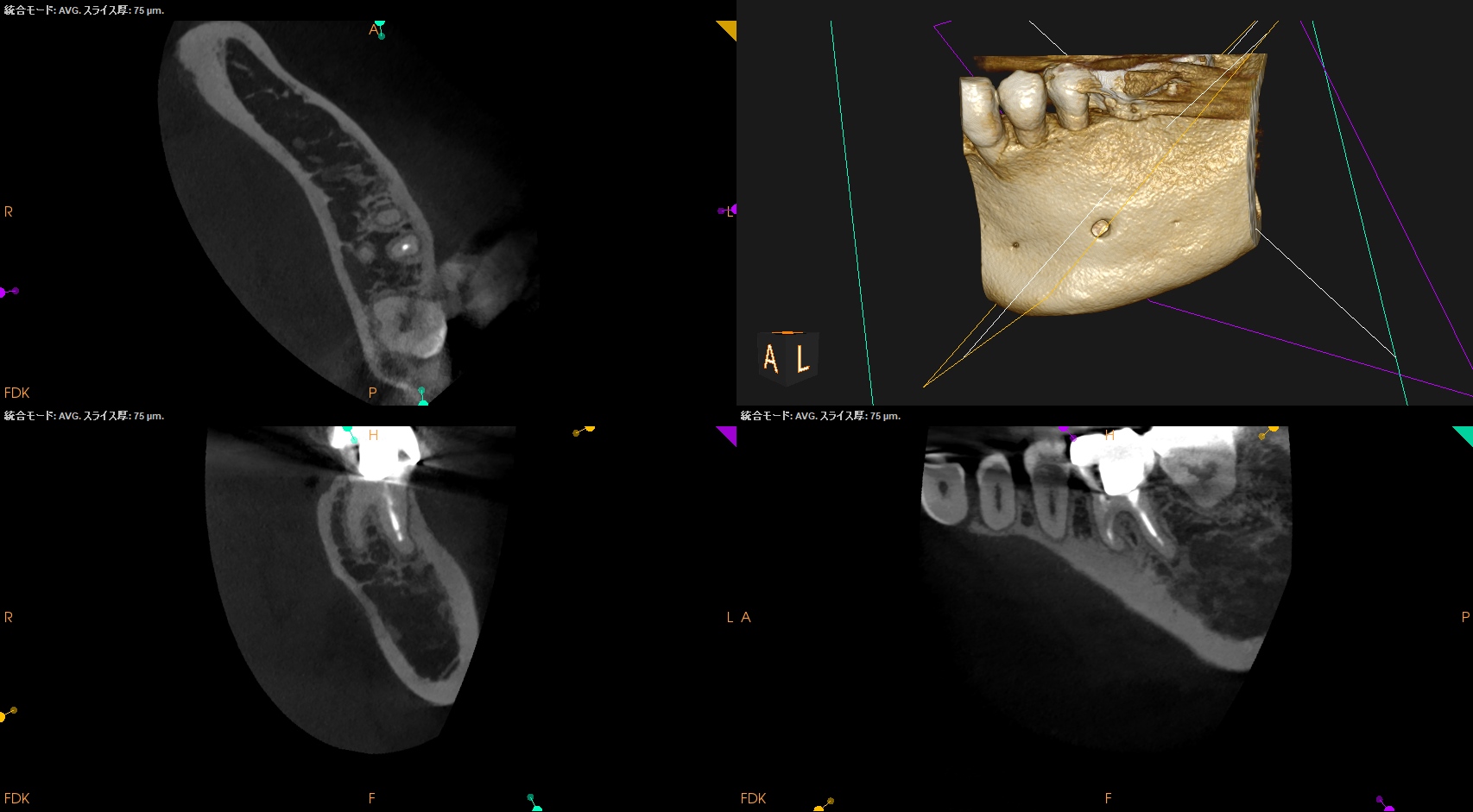先日の記事の続報。
#18の痛みは根管治療で除去可能だが、
歯内療法学的検査(2025.4.30)
#18 Cold++1/5, Perc.(+), Palp.(-), BT(+), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)
#19 Cold N/A, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)
#30 Cold+3/1, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)
#31 Cold+5/3, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)
そもそも治療を依頼された#19には何の痛みもない。
これでは治療にならないではないか?という思いがある。
PAは以下だ。

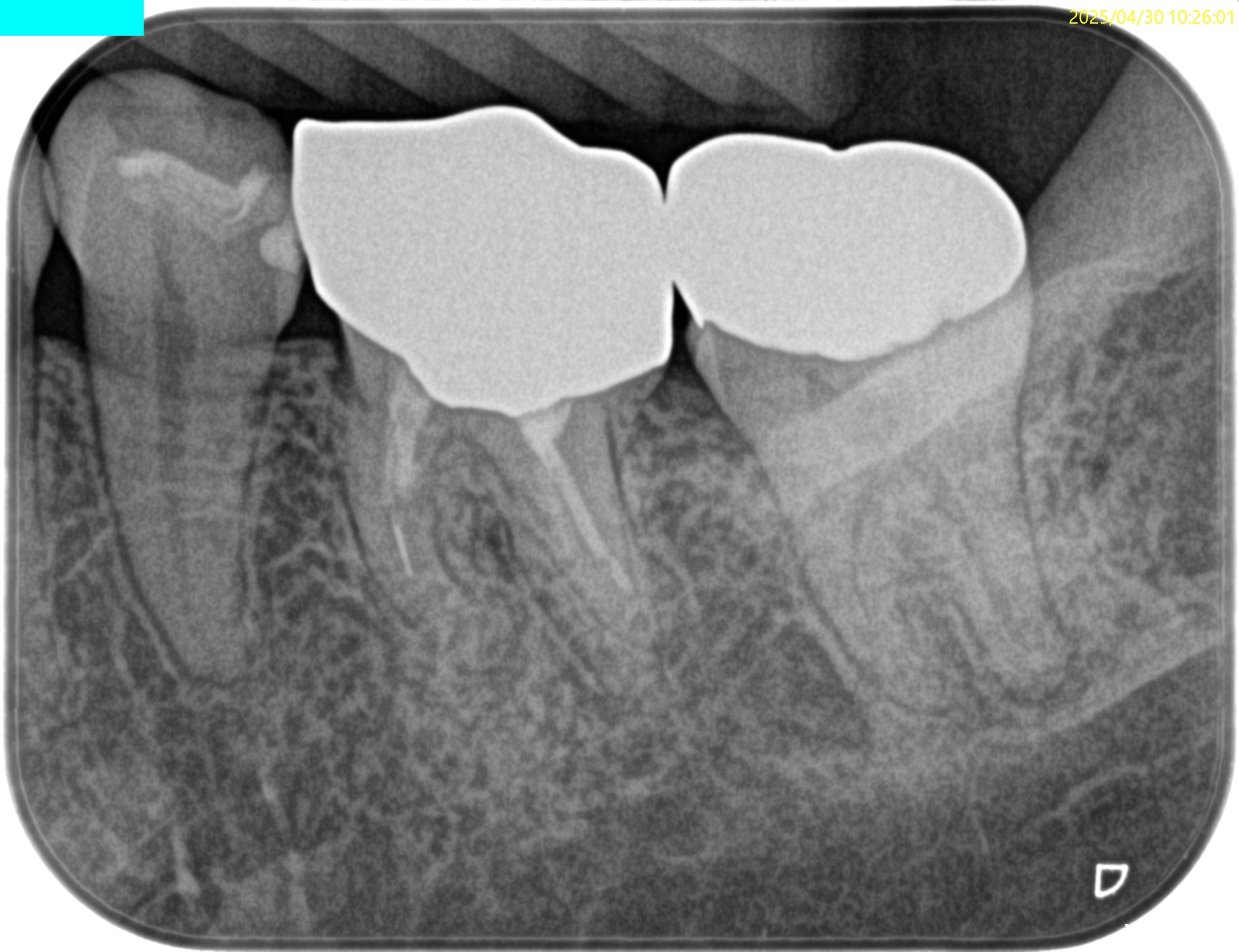
#19の根尖部にはにも見えない。
が、Fileが破折していることはわかる。
しかし、何もないのだ。
私自身もかつて根管治療によりFileが折られて右下の歯槽骨にそれが浸かっているが問題がない
ではCBCTはどうだろうか?
#19 MB
#19 ML
MBとMLの間にはMMがあるようだ。
CBCTだとここまで術前にわかる。
#19 MM
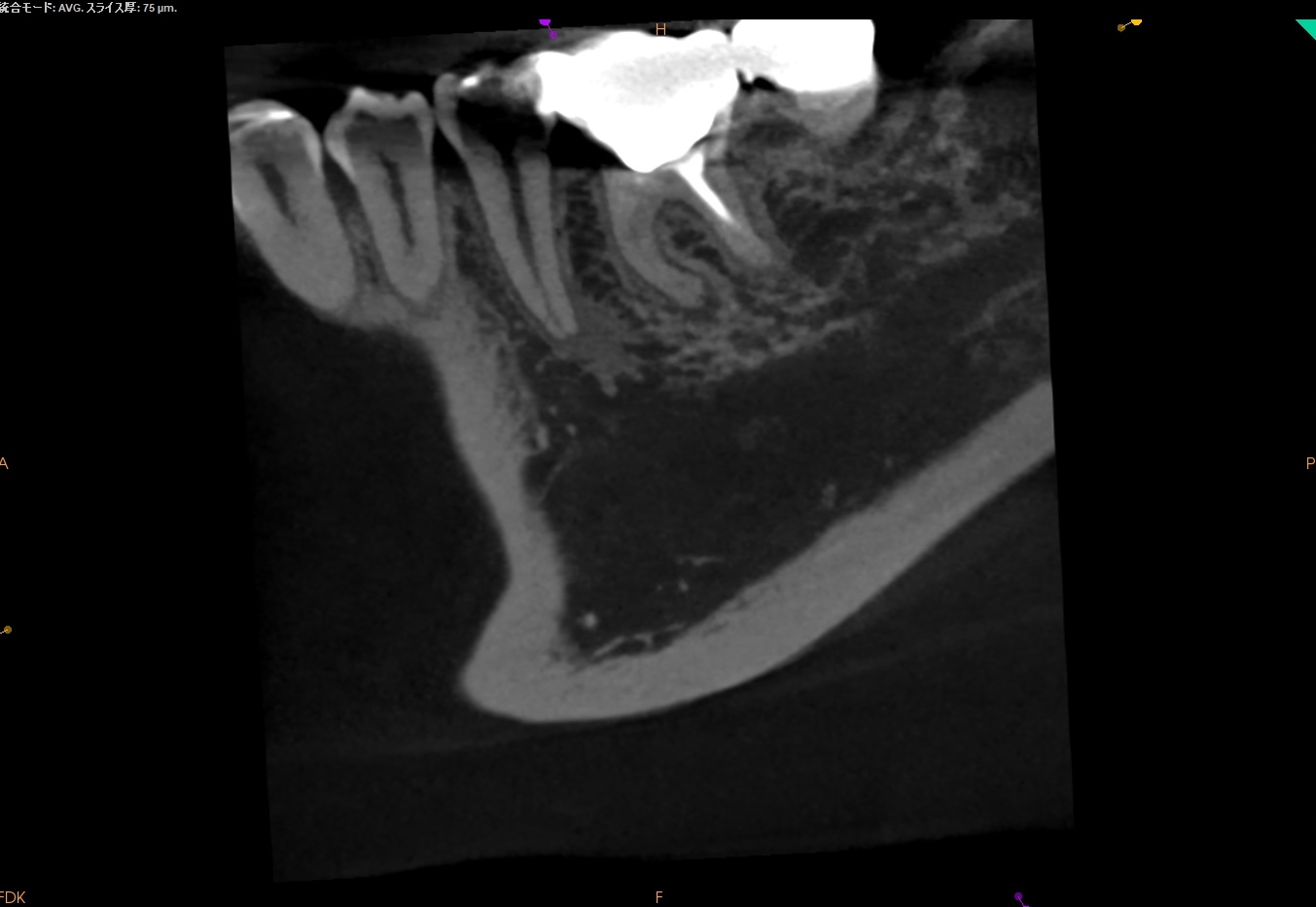
そしてApex付近に病変がある。
MMが未形成で根尖病変ができている。
ここは攻略が必要そうだ。
この探し方は後述する。
#19 D
#19 Radix
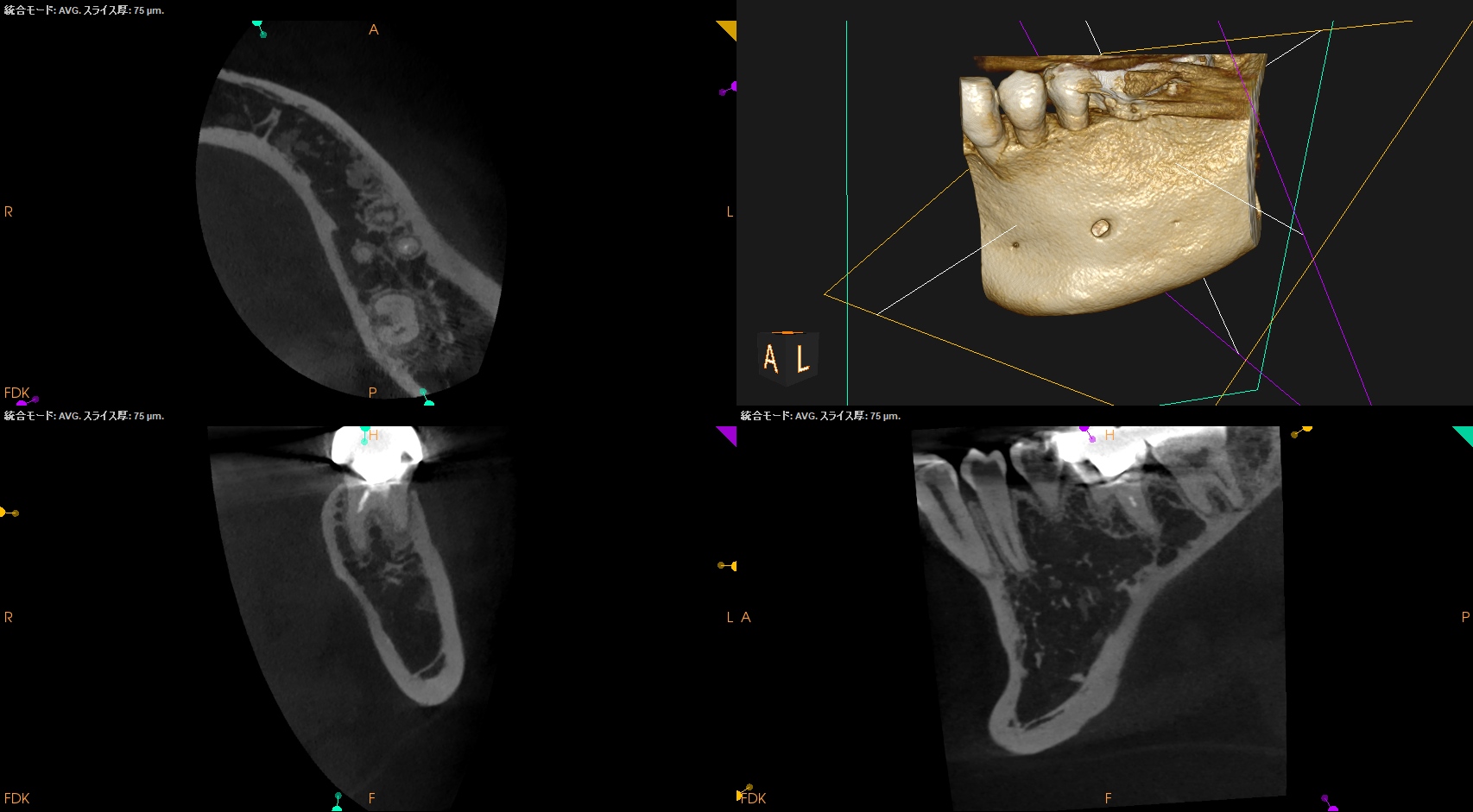
D,Radixには病変がない。
以上より、
MMのみ攻略すればいい
という話である。
が、MMをどうやって見つけていくのだろうか?
Azim 2015 Prevalence of middle mesial canals in mandibular molars after guided troughing under high magnification: an in vivo investigation.
によれば、
In vivo(clinical)で91本の下顎大臼歯を根管治療している。
この際に、マイクロスコープを通じてMBとMLの間を
Munce Discovery Bur
を使用して、
2mm程度そこを削合してMMを探索している。
すると、MMはそれをしない場合よりも約7倍の確率で発見できている。
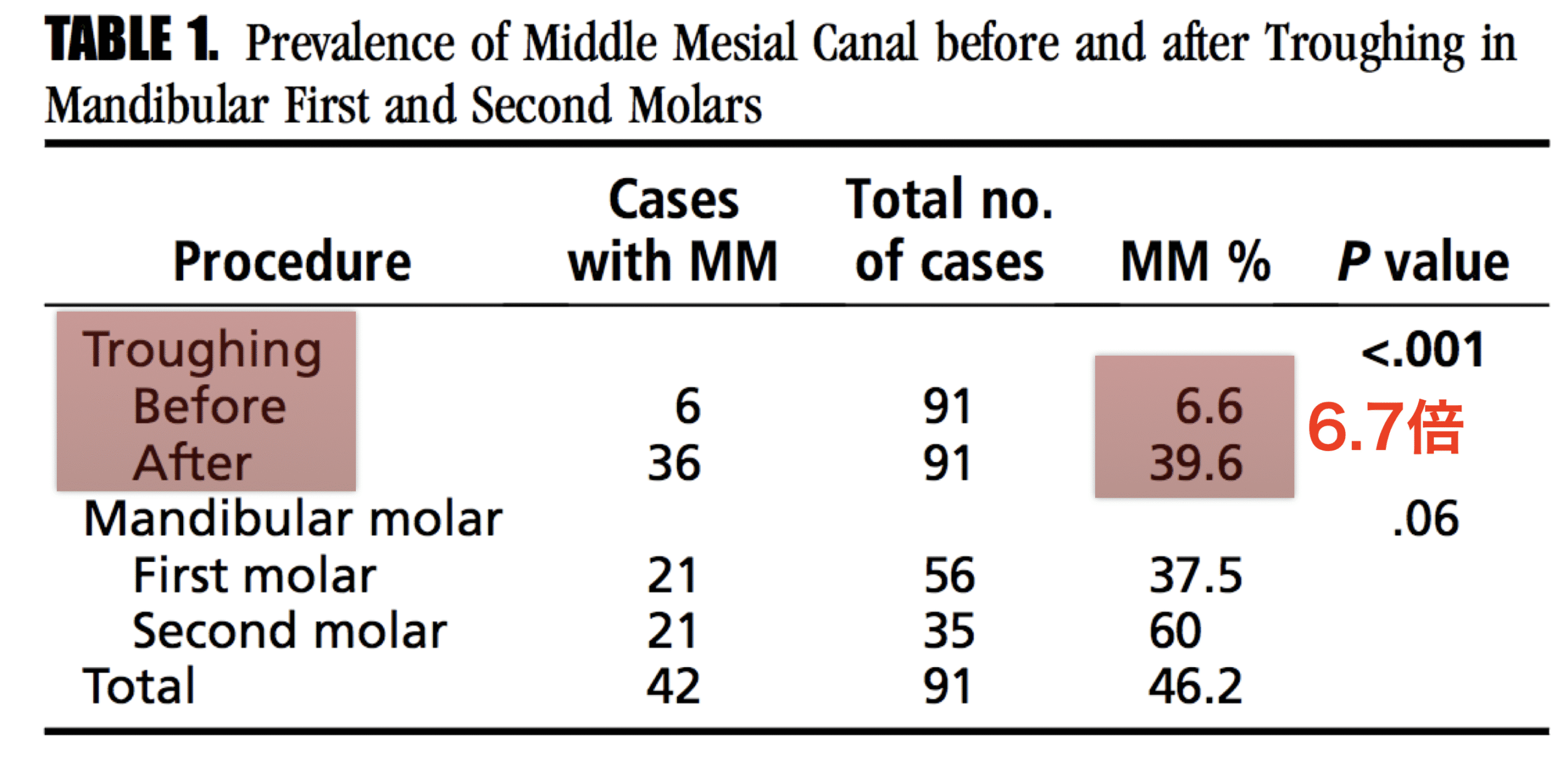
また、MM根管には以下のような特徴がある。
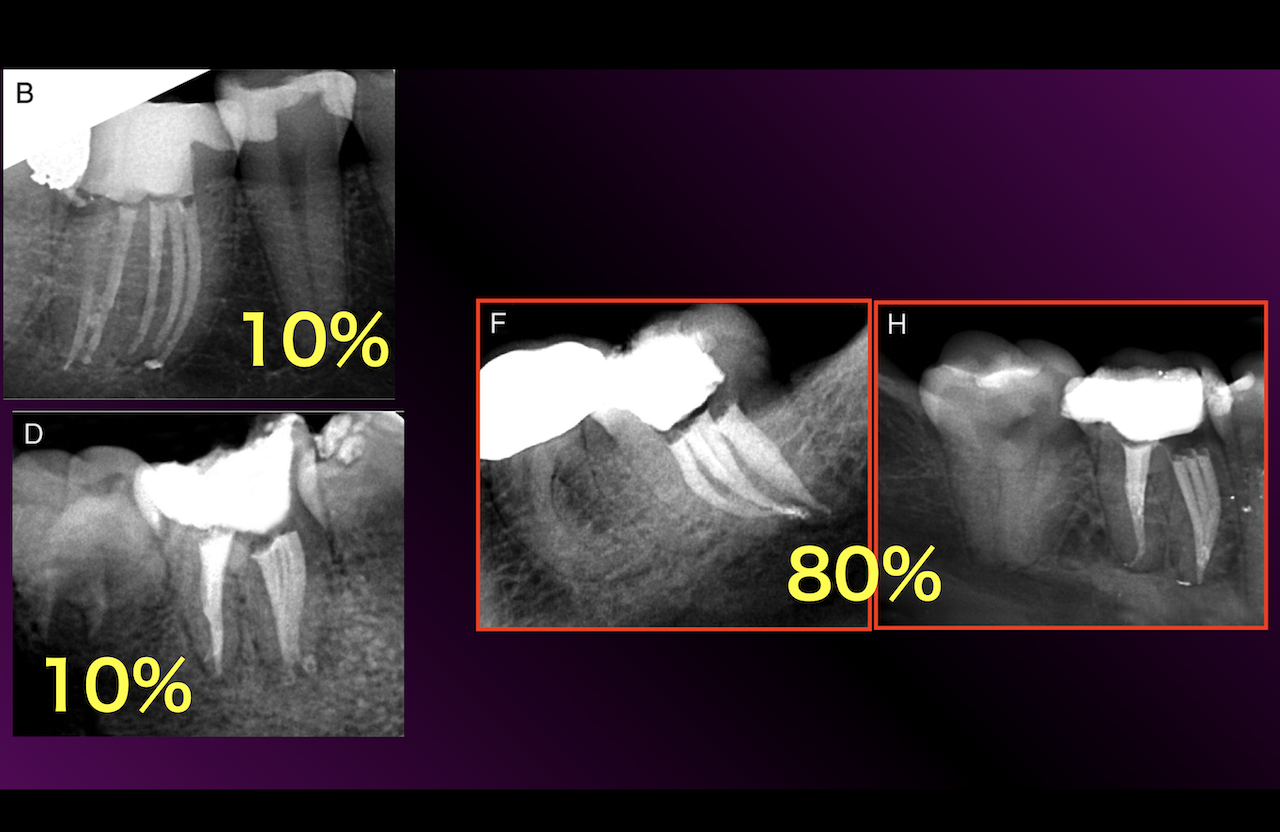
いわゆる
イカの足
みたいになることは
10%程度しかない
という臨床的事実だ。
あればそれは、Board Caseと言われる類の治療だろう。
また、MMはそのほとんどがApical Foramenまで根管が連なっている。
ここが80%が合流すると言われているMB2との大きな違いかもしれない。
言い換えれば、
MMを見つけてそこを根管形成・根管充填すればこの根尖病変はマネージメントできる可能性がある
ということがわかる。
つまりこの歯の治療は、
事実上のInitial RCTであるが、その際に周囲のGutta Percha Pointをマップにしてそれを探索するという必要があるのである。
この言葉の意味があなたにはわかるだろうか?
#19 歯内療法学的診断(2025.4.30)
Pulp Dx: Previously treated
Periapical Dx: Asymptomatic apical periodontitis
Recommended Tx: Re-RCT
というわけで、同日に治療へ移行した。
⭐︎この後、治療動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。
#19 Re-RCT(2025.4.30)
再根管形成の前にメタルポストを除去する必要がある。
この後、MMを探索する。その方法は前述の通りだ。
MMはML寄りにあることが多い。
思しき部位をDo Well Dentalの先の鋭く細い短針(先端#17)を挿入した。
SXを根管形成で破折させないための
スカウティング
である。
MMをProTaper Gold SXで形成した。
MMはC+ File #6で穿通した。
そして湾曲が比較的強いことから、
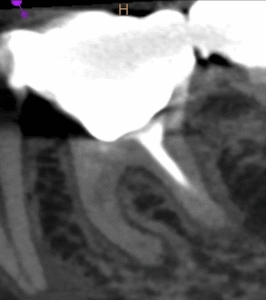
HyFlex EDM #20.05→#25.V→#40.04まで形成する!と, 穿通した瞬間に決定した。
この後、MLかMBも形成しようと試みるが、MBを穿孔させてしまう。
いわゆるストリッピングパーフォレーションだ。
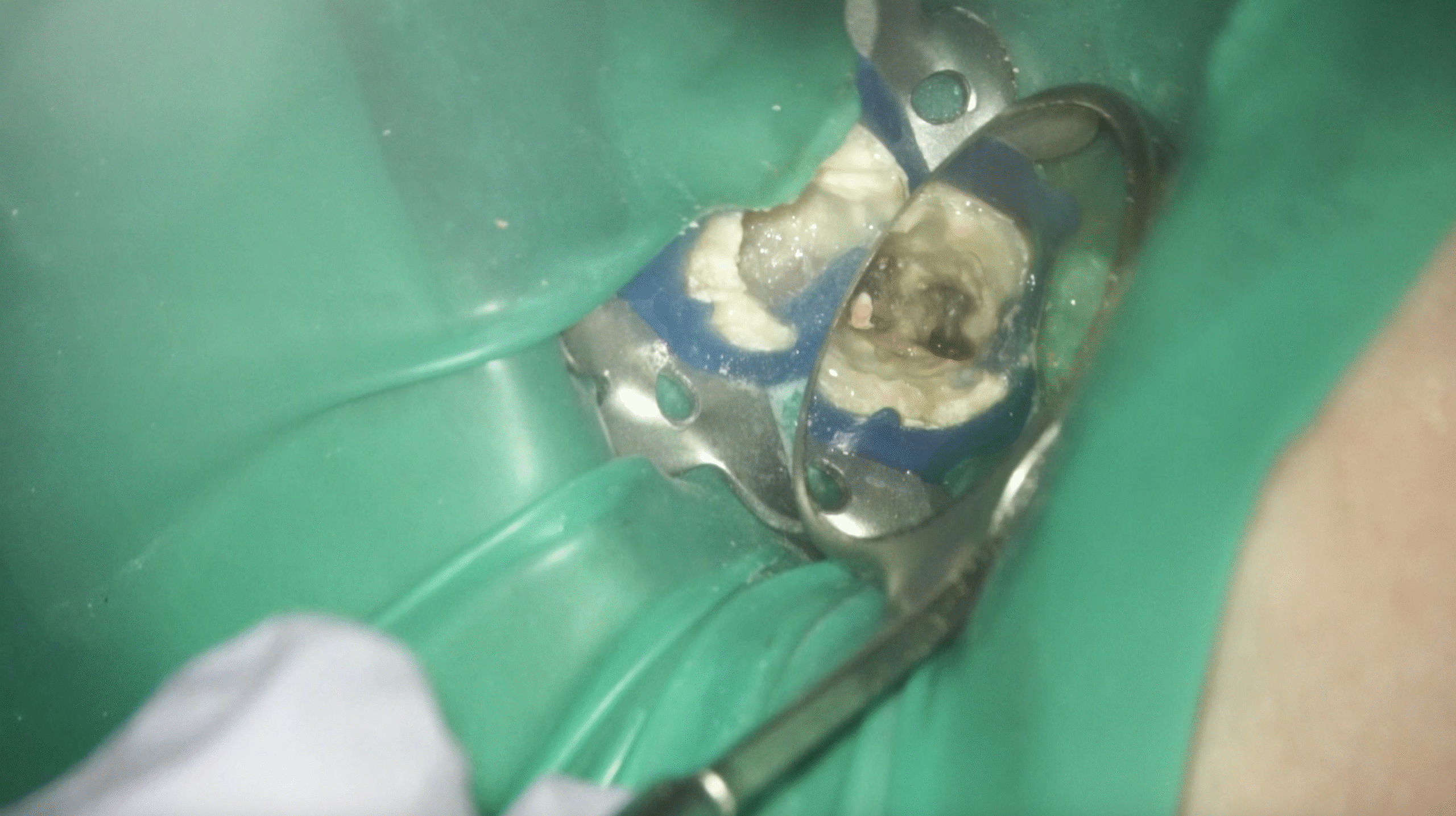
予後に大きく影響するが、それはそれを放置した場合である。
即座に封鎖すれば問題はない。
どうやって?と言えば、
MMを根充時にBioceramic sealerで一緒に封鎖してしまえばいいのでそれほど問題もないだろう。
ということでこの治療の作業内容は以下になった。
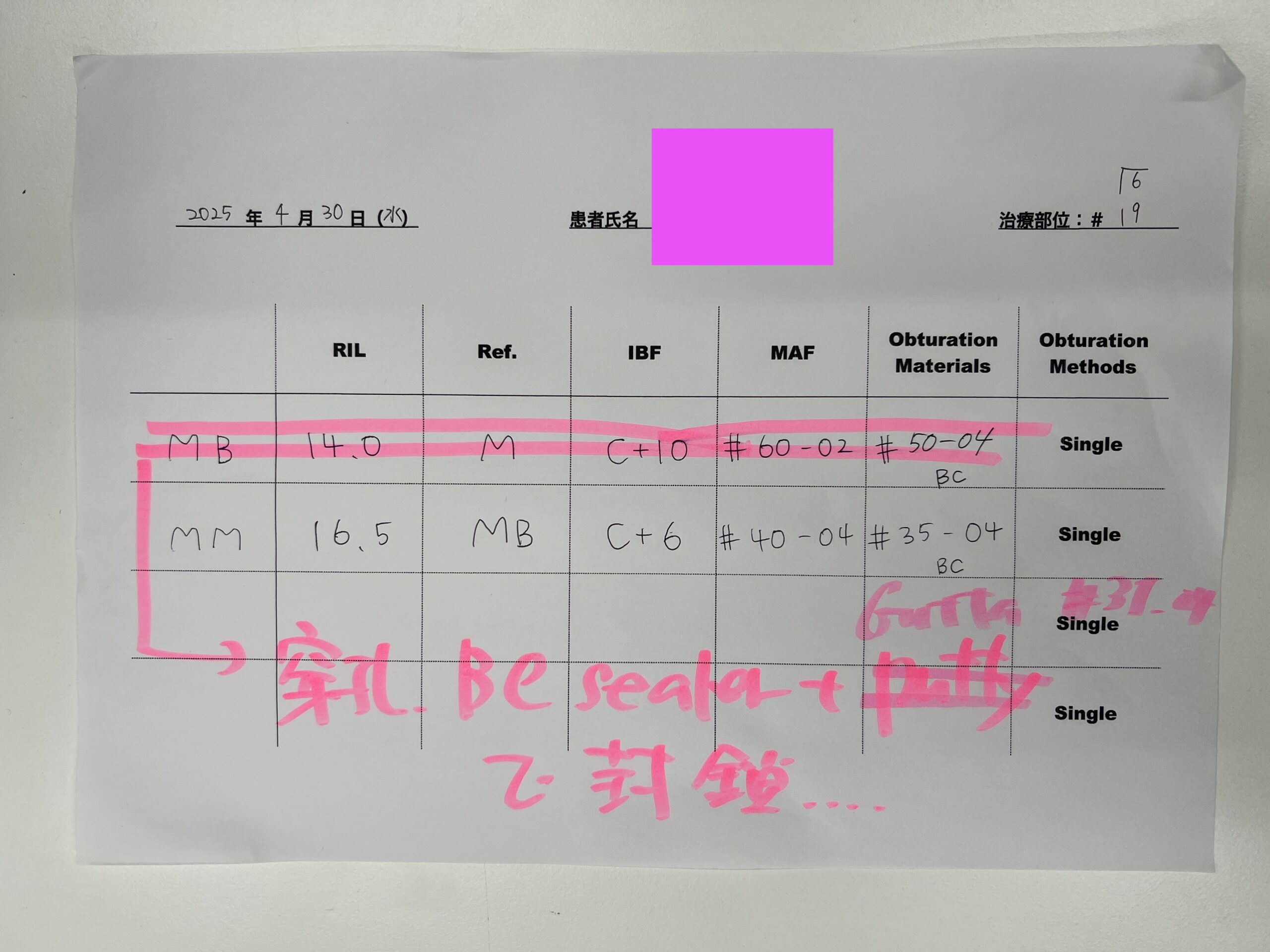
根管充填した。
MB部はパテを使用せずにそのまま根管充填した。
根充時のシーラーが穿孔部を埋めてくれるであろうから問題ないと判断している。
術後にPA, CBCTを撮影した。


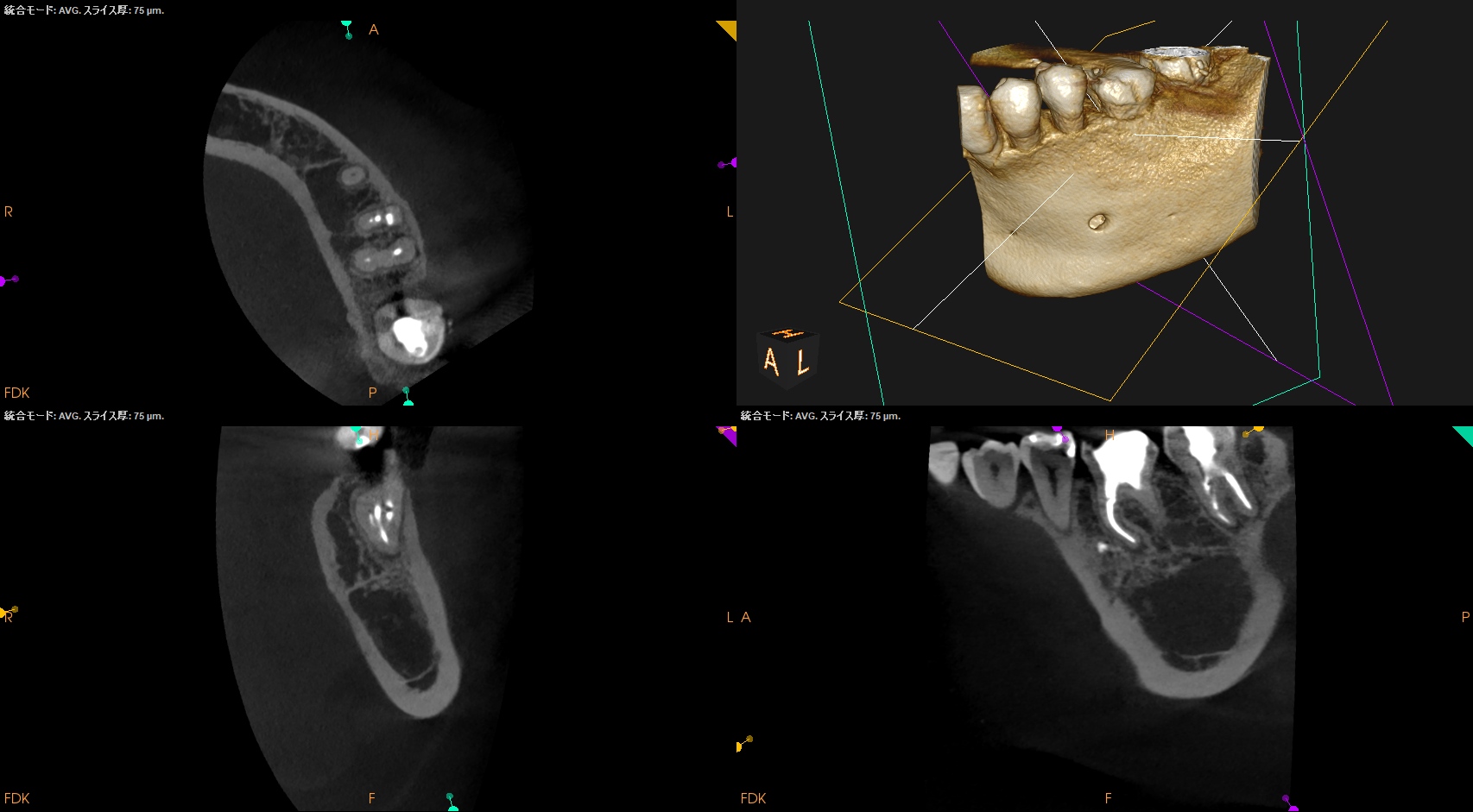
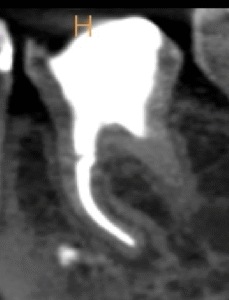
湾曲が強いことがわかるだろう。
そしてこのMMもML寄りにあることがわかる。
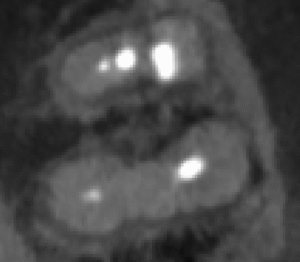
これで問題(術前の小さな根尖病変)が解決するかどうか?は1年後にわかる。
またその模様はお伝えしたい。