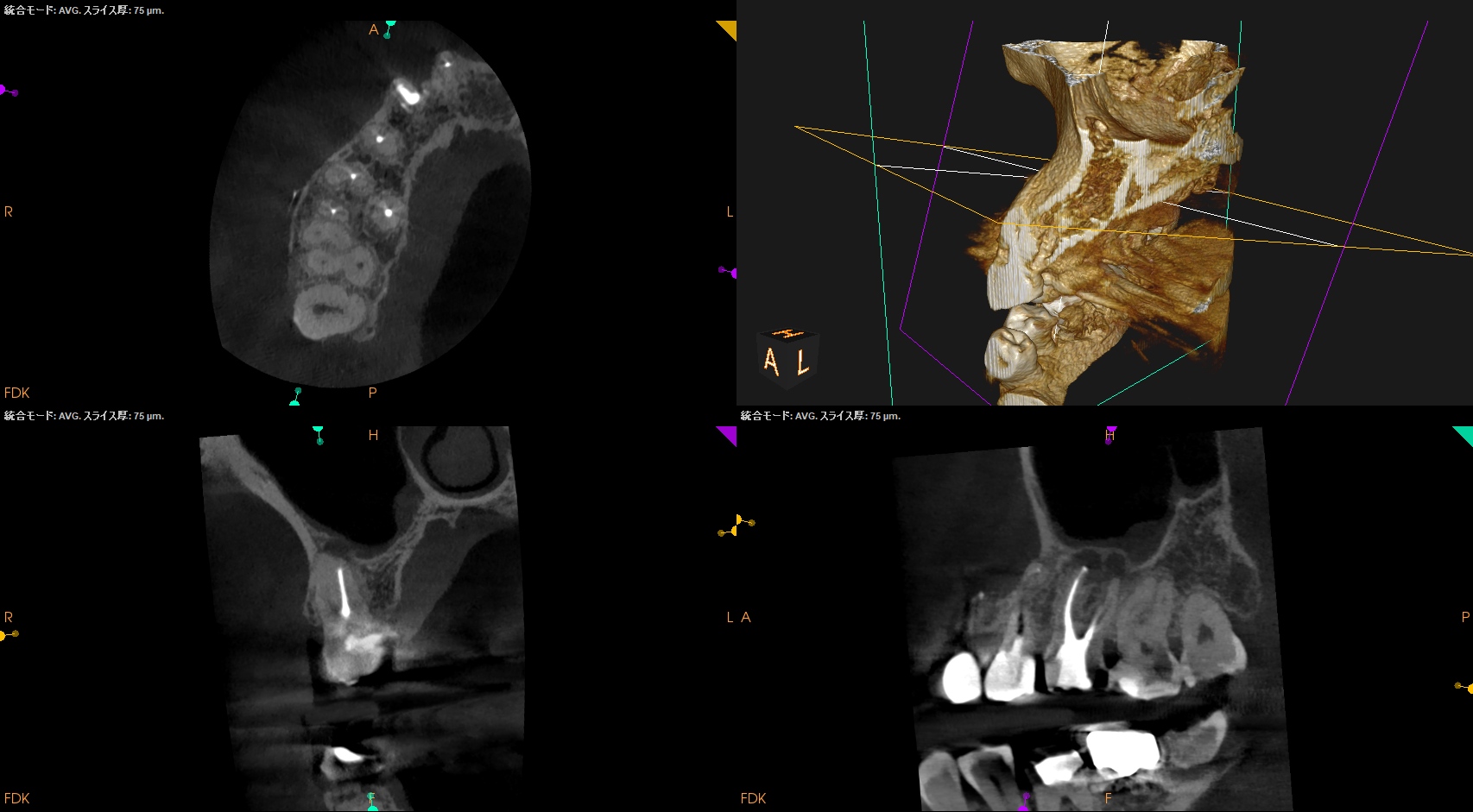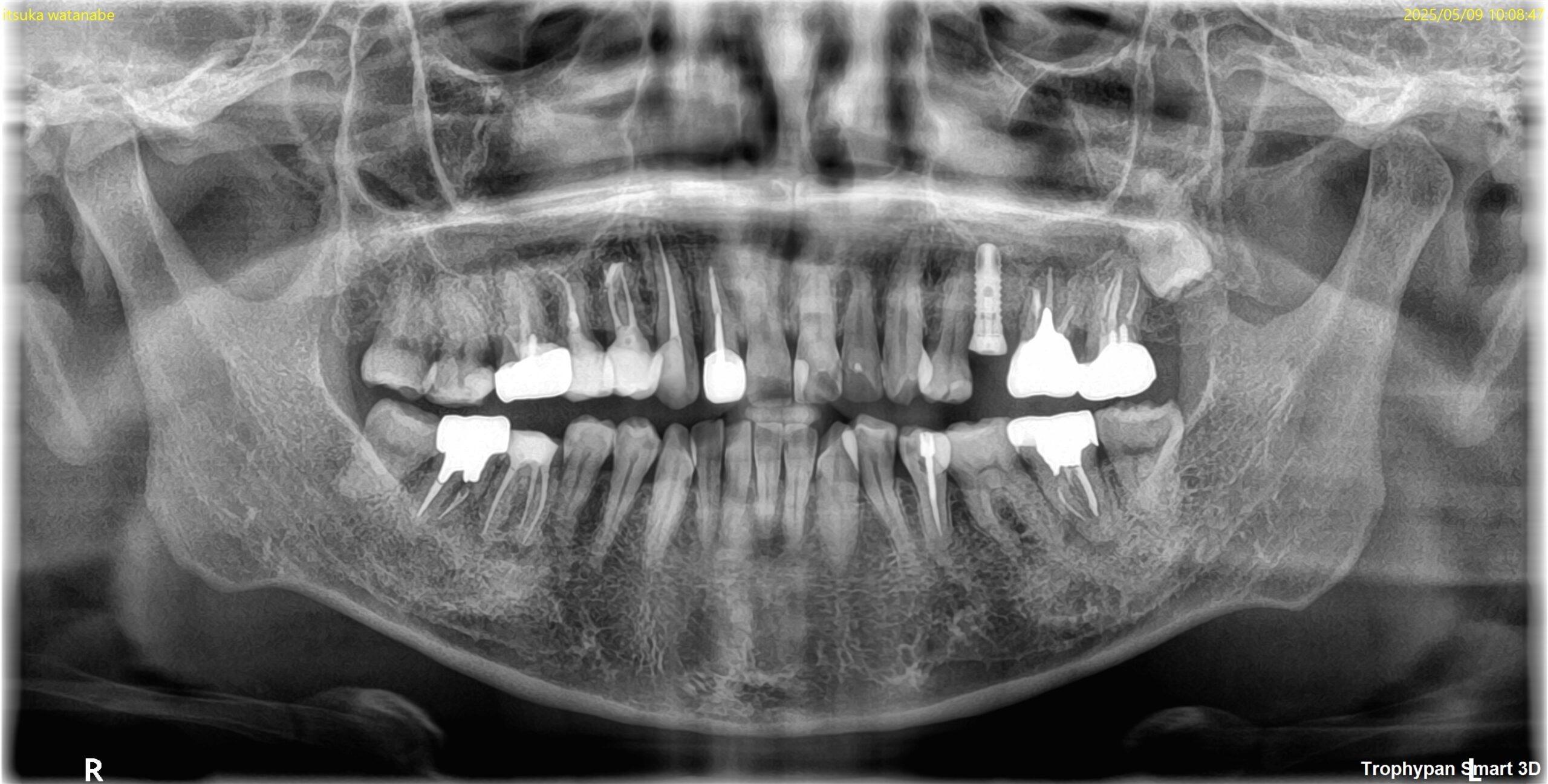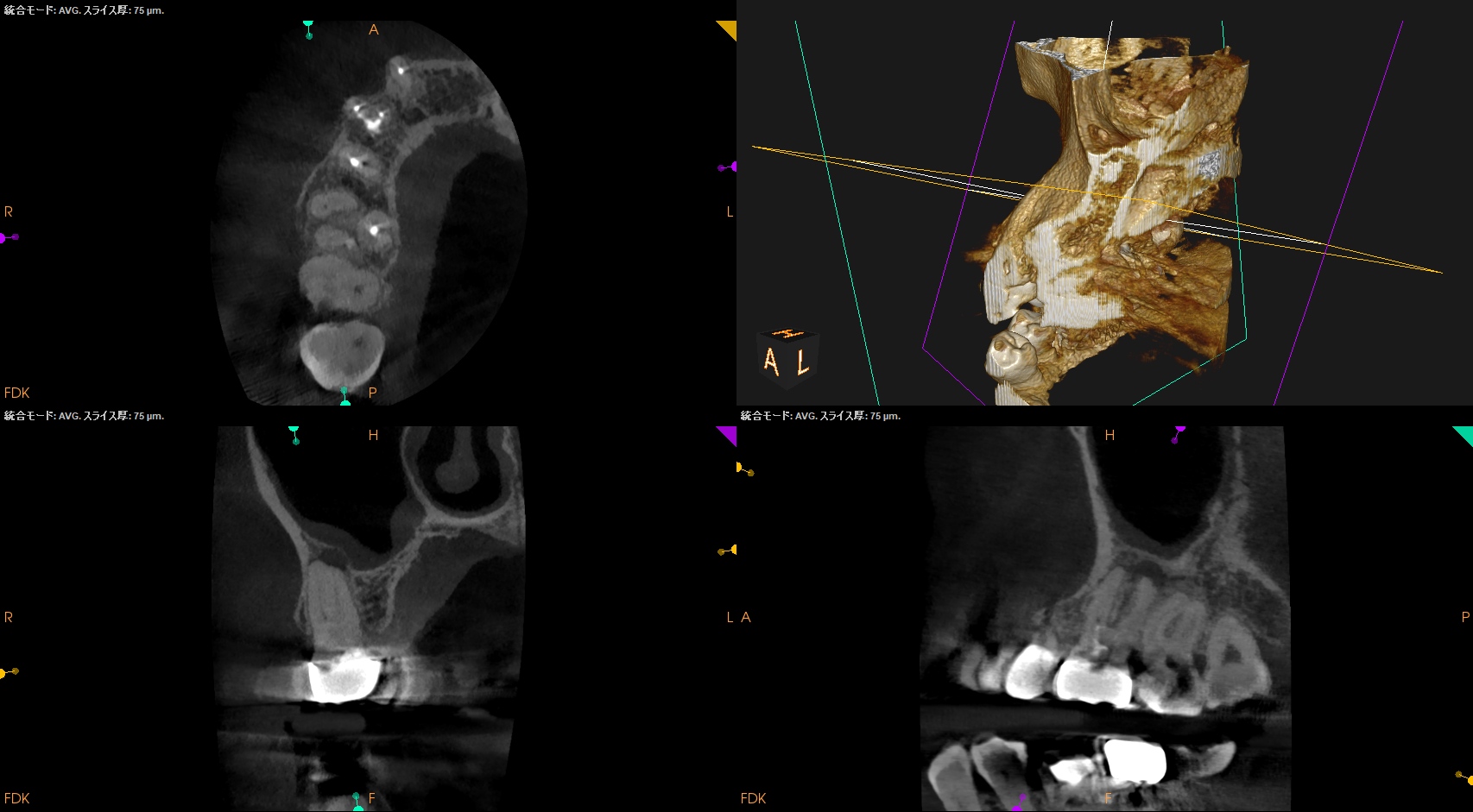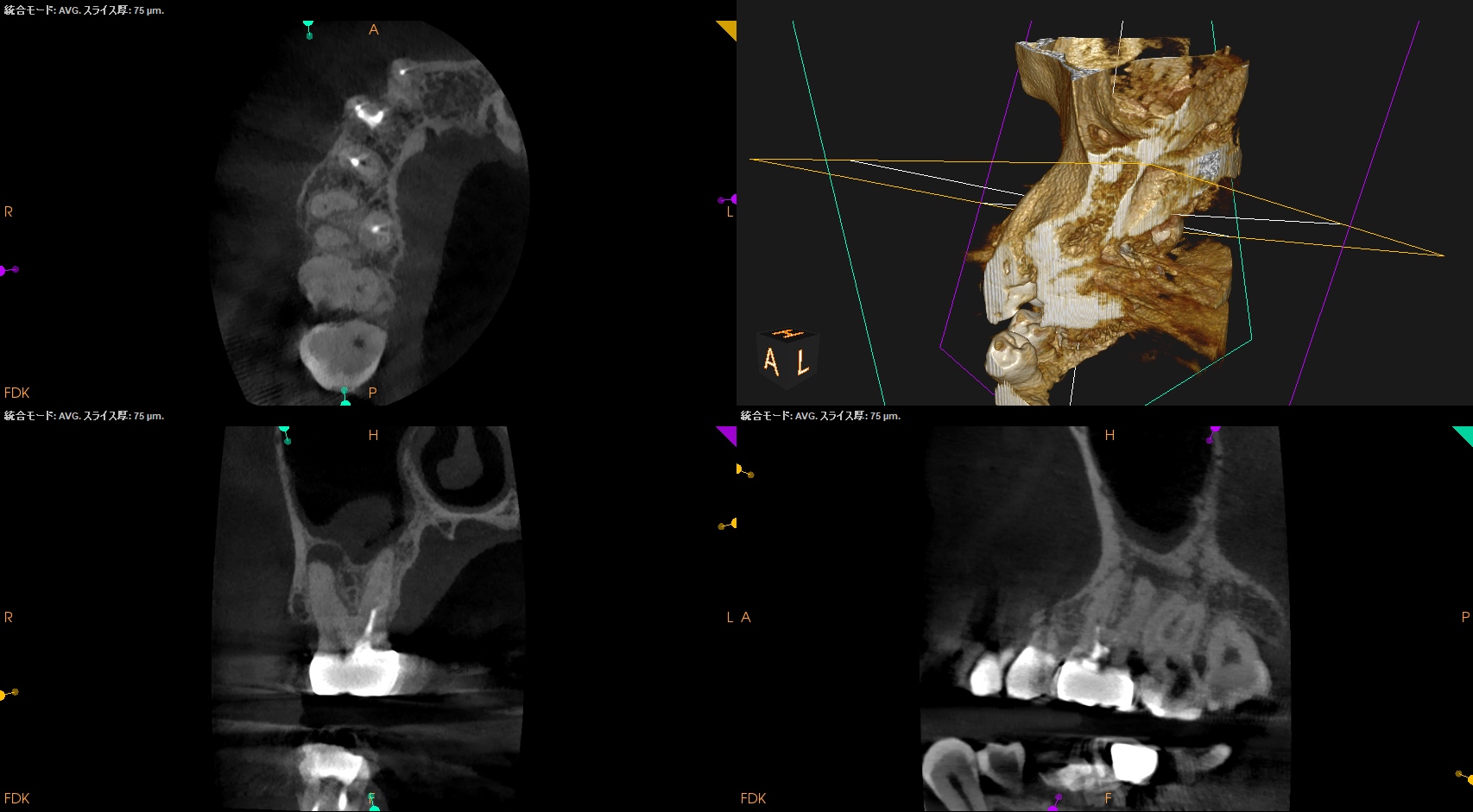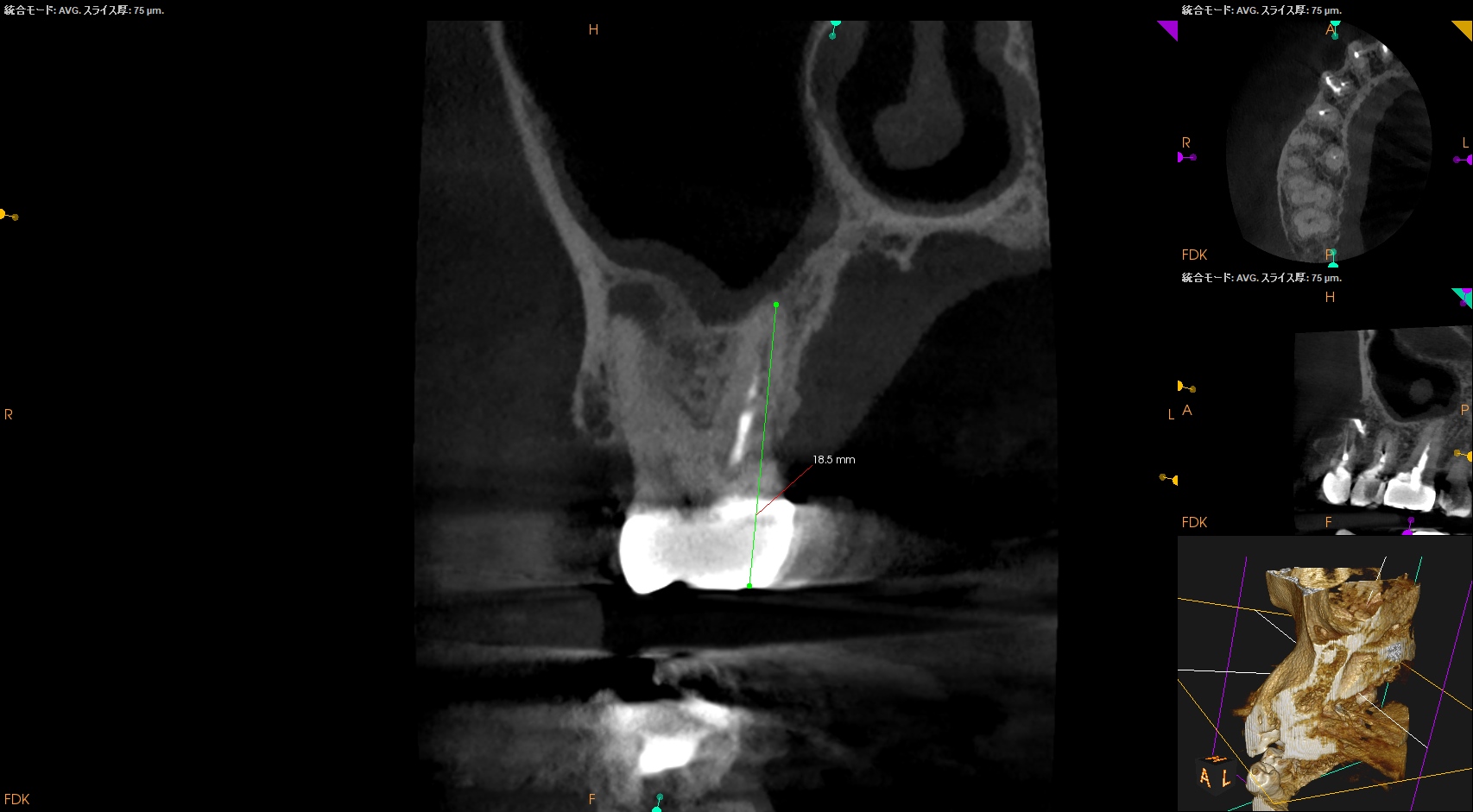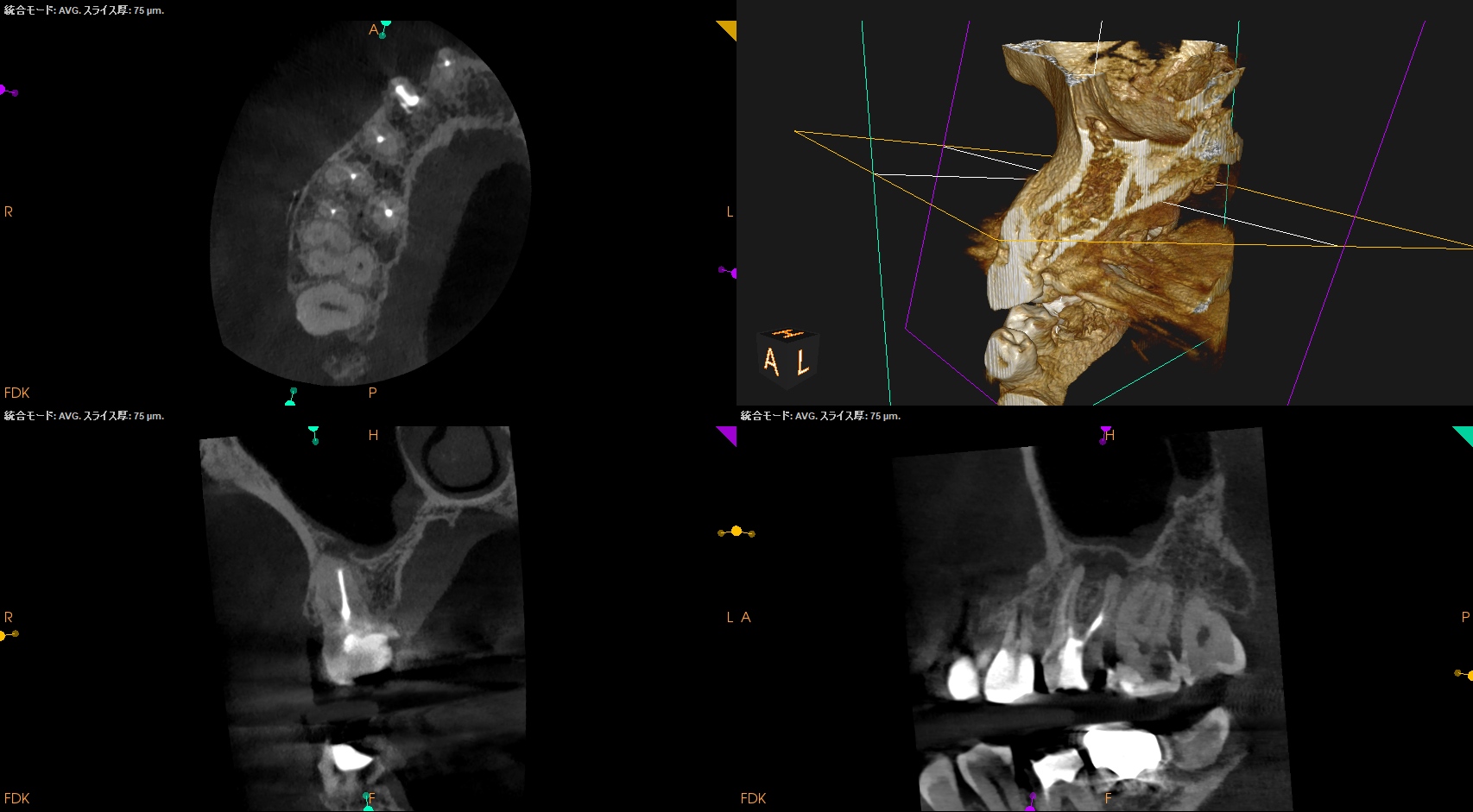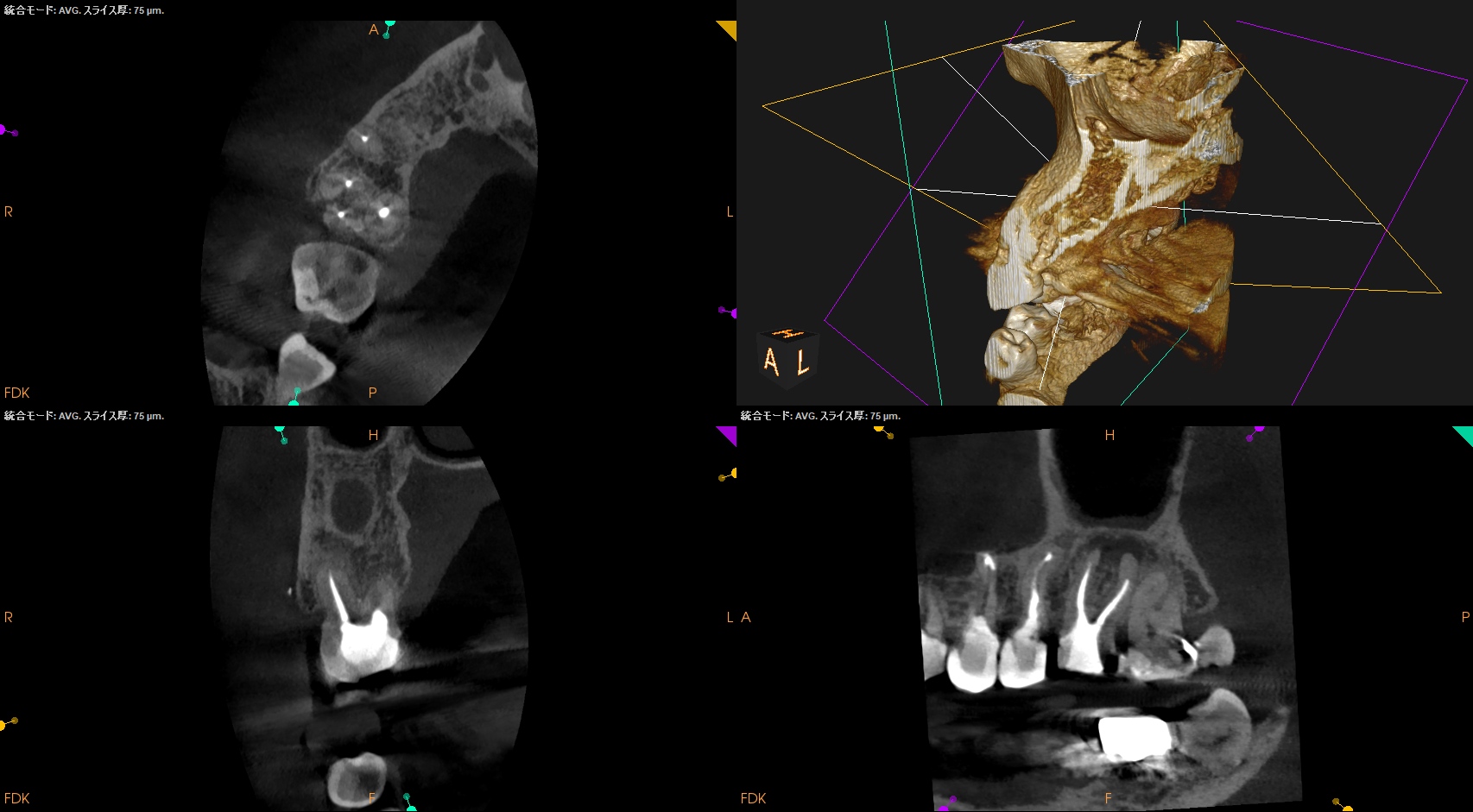紹介患者さんの治療。
主訴は、
数週間前、治療した歯が痛くなりものが噛めなくなった。
である。
歯内療法学的検査(2025.5.9)
#2 Cold+1/4, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)
#3 Cold N/A, Perc.(+), Palp.(-), BT(+), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)
主訴は#3のようだ。
PA(2025.5.9)
Ortho Pantomo Graph(2025.5.9)
CBCT(2025.5.9)
#3 MB
#3 MB2

#3 DB
#3 P
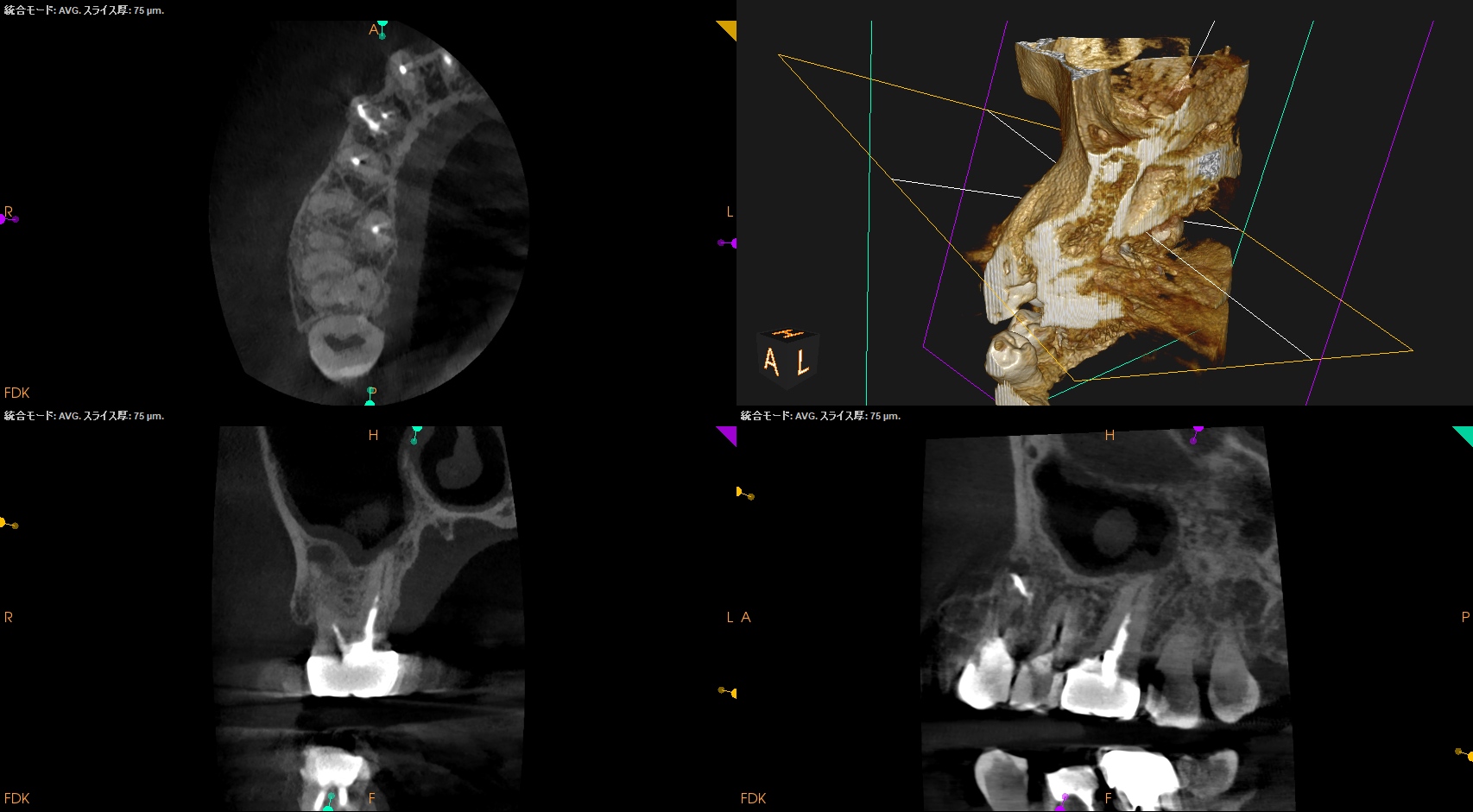
MB2, DB, Pに病変があり、根管形成が十分になされていない。
ということは…
Previously initiated therapyのRCTということになる。
同日、治療へ移行した。
歯内療法学的診断(2025.5.9)
Pulp Dx: Previously initiated therapy
Periapical Dx: Symptomatic apical periodontitis
Recommended Tx: Re-RCT
☆この後、治療動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。
#3 Re-RCT(2025.5.9)
まず、Screw pinを除去する。
その方法は、メタルポストコアと同等だ。
詳細は、
Basic Course 2025
で解説します。
スクリューピンを除去したら、レジンコアの除去だ。
レジンコア除去を嫌がる臨床家が多い。
曰く、
外しにくい
という。
それは、
前医が防湿をきちんとした環境(ラバーダム防湿下)でやっていれば
という条件がつく。
私が知るかぎり、そのような環境=ラバーダム防湿環境下 でレジンコアを築造する臨床家はほぼいない。
ということは、
レジンを薄く削合し鋭い短針で突けば、塊で除去できることが多い
のである。
下記動画を参考にされたい。
難しいことだろうか?
最後は根管バキュームで近心のレジンを押すとそれが塊で除去できた。
この後、歯牙を精査するが健全歯質がほとんどないのでレジンで隔壁形成(Temporary Core Build up)した。
ラバーダムしたいが無理であるので , Zooで簡易防湿して隔壁形成した。
これでようやく、再根管治療ができる。
このことからしても、初期治療より再治療の方が時間がかかる。
が、保険点数は再根管治療の方が低い。
これで大丈夫か?と思うが、もはやどうすることもできないだろう。
さておき、ラバーダム防湿し、P根、DB根、MB根と再根管形成した。
長さを測定してないじゃないか?というあなた。
長さは以下のように測定する。
P
DB
MB

Reference PointからApexまでの長さを測定し、メジャリングデバイスを使用してクラウンの厚みを測定し、その引いた長さの-1mmを仮の作業長としてGutta Percha Point除去の長さに設定し、再根管形成をする。
残ったGutta Percha PointはC-solutionを浸してC+ Fileで穿通を試みる。
私が思うに、これが最速だ。
しかし、いずれにしても
CBCTがなければできない技だ。
それぞれの根管を#25.Vでまず再根管形成した。
この際のラバーストップとReference Pointの距離と(度合い)と術前の根尖病変の有無で、MAFが決まる。
根尖病変はPにはないので、MAFは#40.04とした。
とすると、一覧表は以下のようになった。
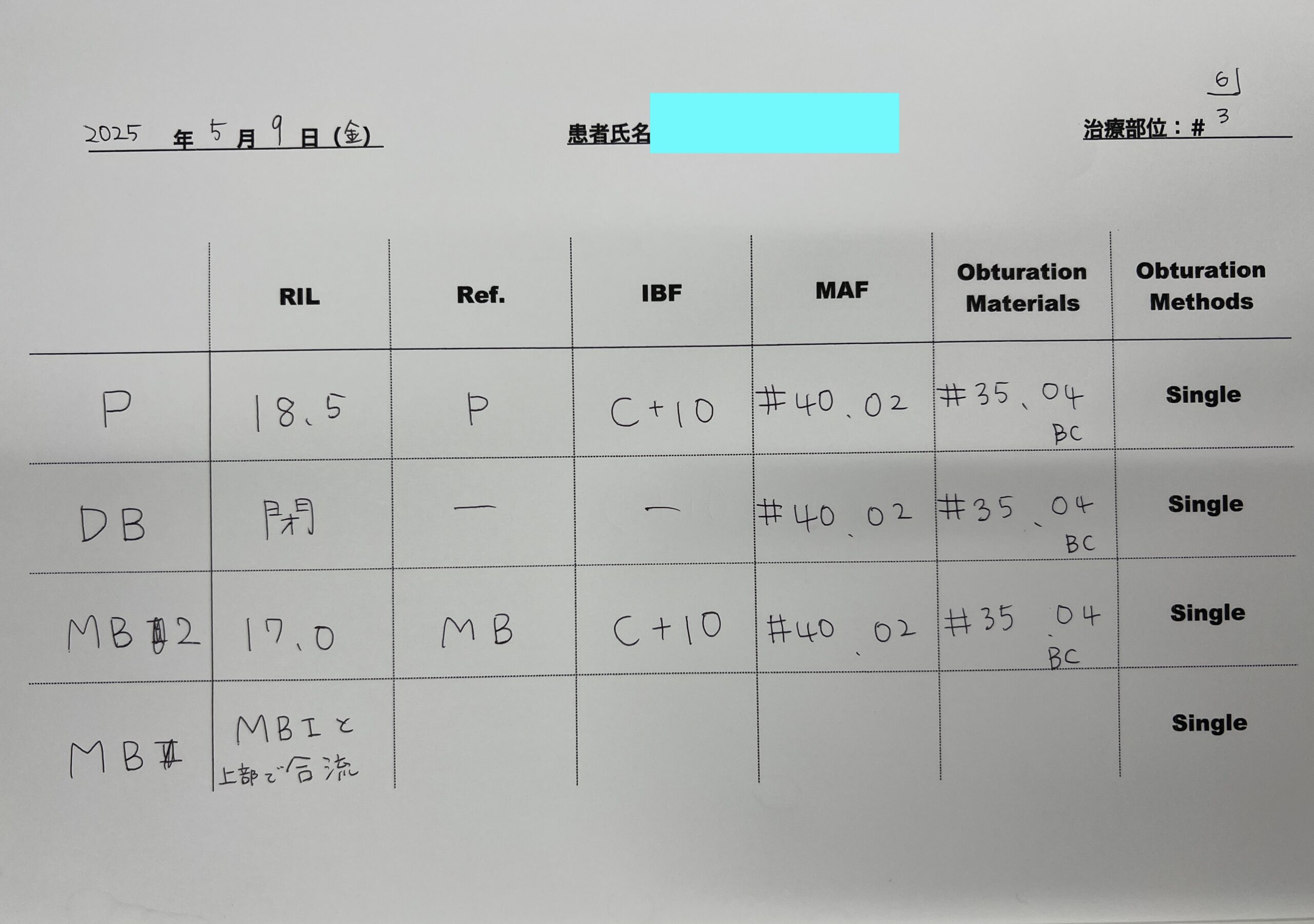
#40.04
MAFまで再根管形成した。
最後に根管充填した。
術後にPA, CBCTを撮影した。


MB1
MB2
MB1!と思い、再根管形成した根管はなんと…MB2だったのだ。
動画を見返すと以下である。

結果論だが、このMBは
Vertucci TypeⅣ
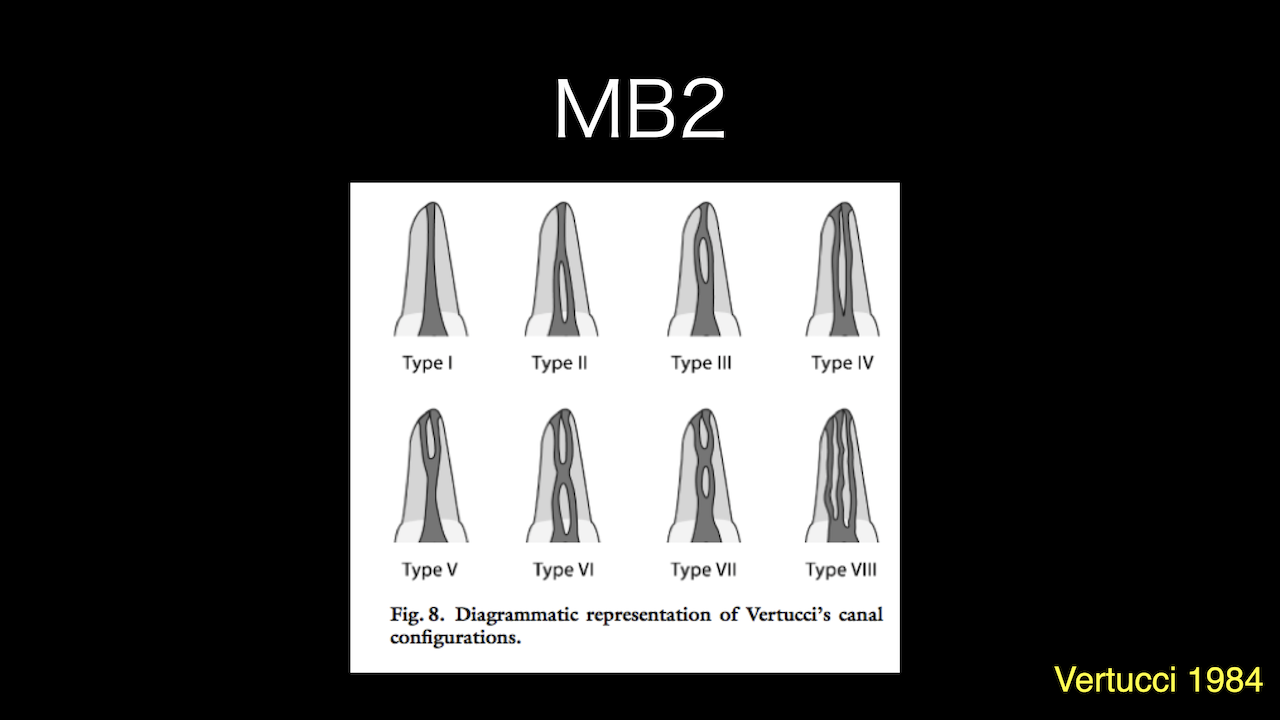
であったのだ。
が,MB2がApical Foramenまで形成できているし、Sealer Puffもある。
ということは、治癒する可能性はあるのである。
が、治癒しないかもしれない。
つまりここから何が言えるか?といえば、
1年時間をおいて治癒しなければ、Apicoectomyでなく、MB1のみを再根管形成すればいい
ということがわかる。
DB
P
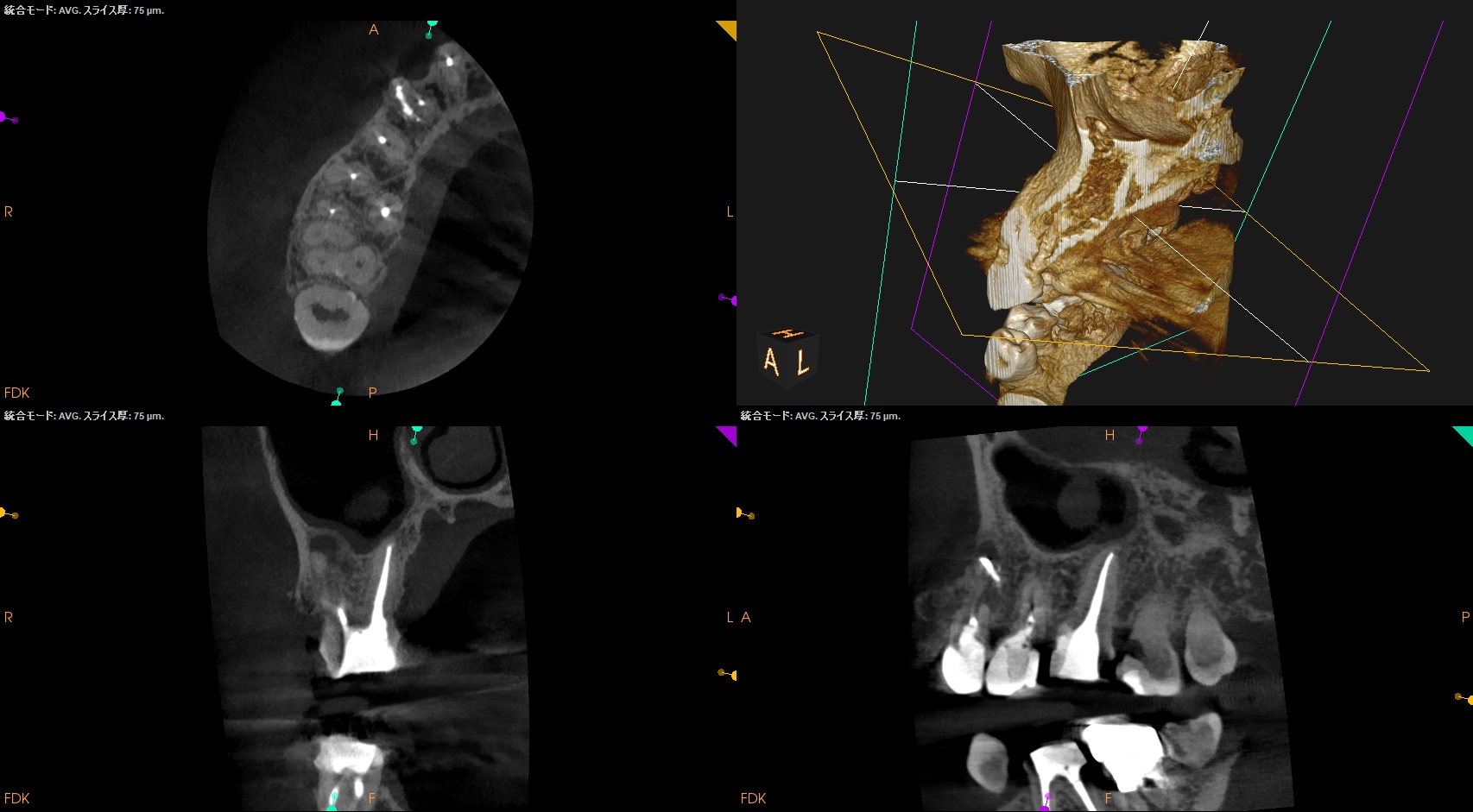
ということで、次回は半年後である。
またこの治療の予後をお伝えしたい。