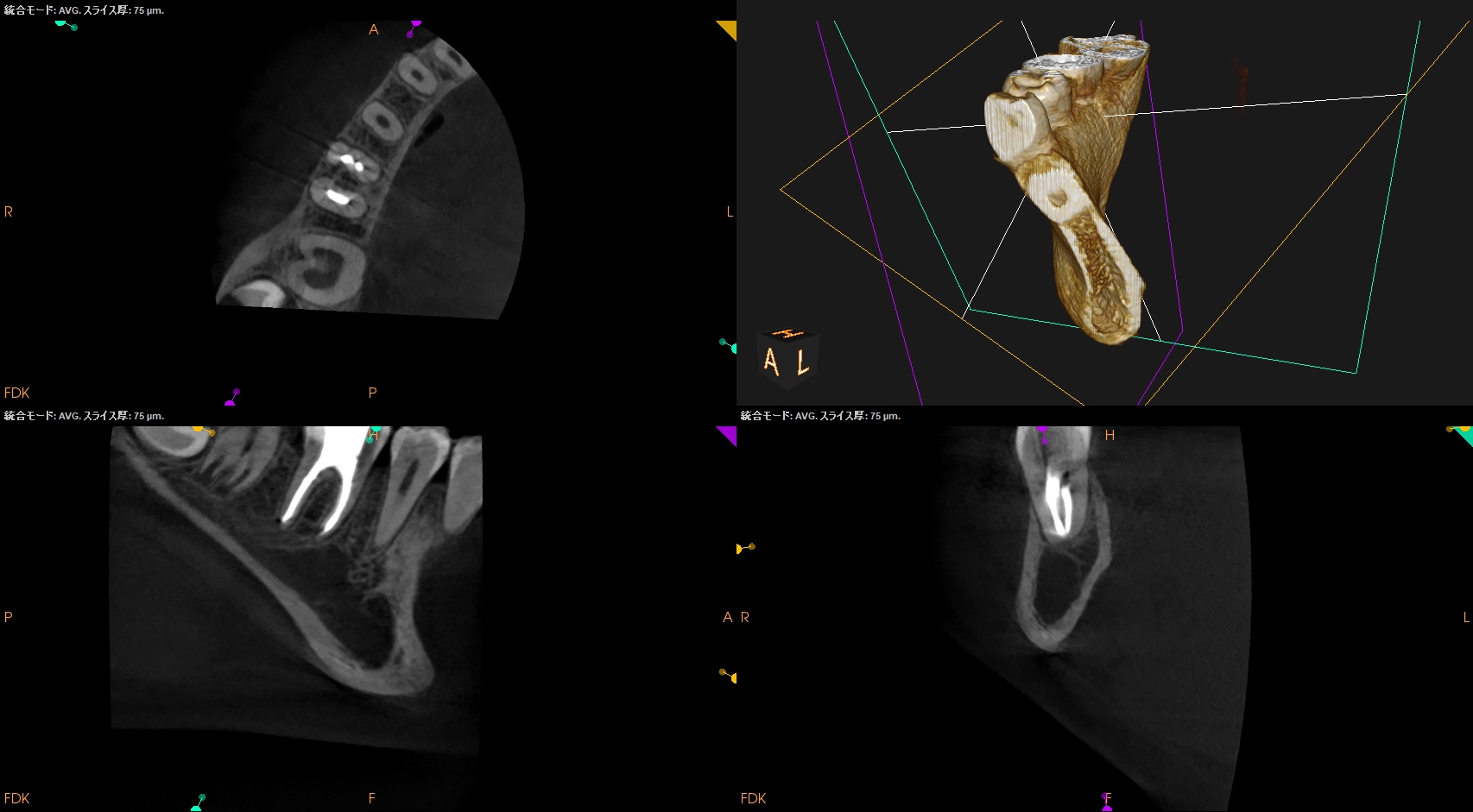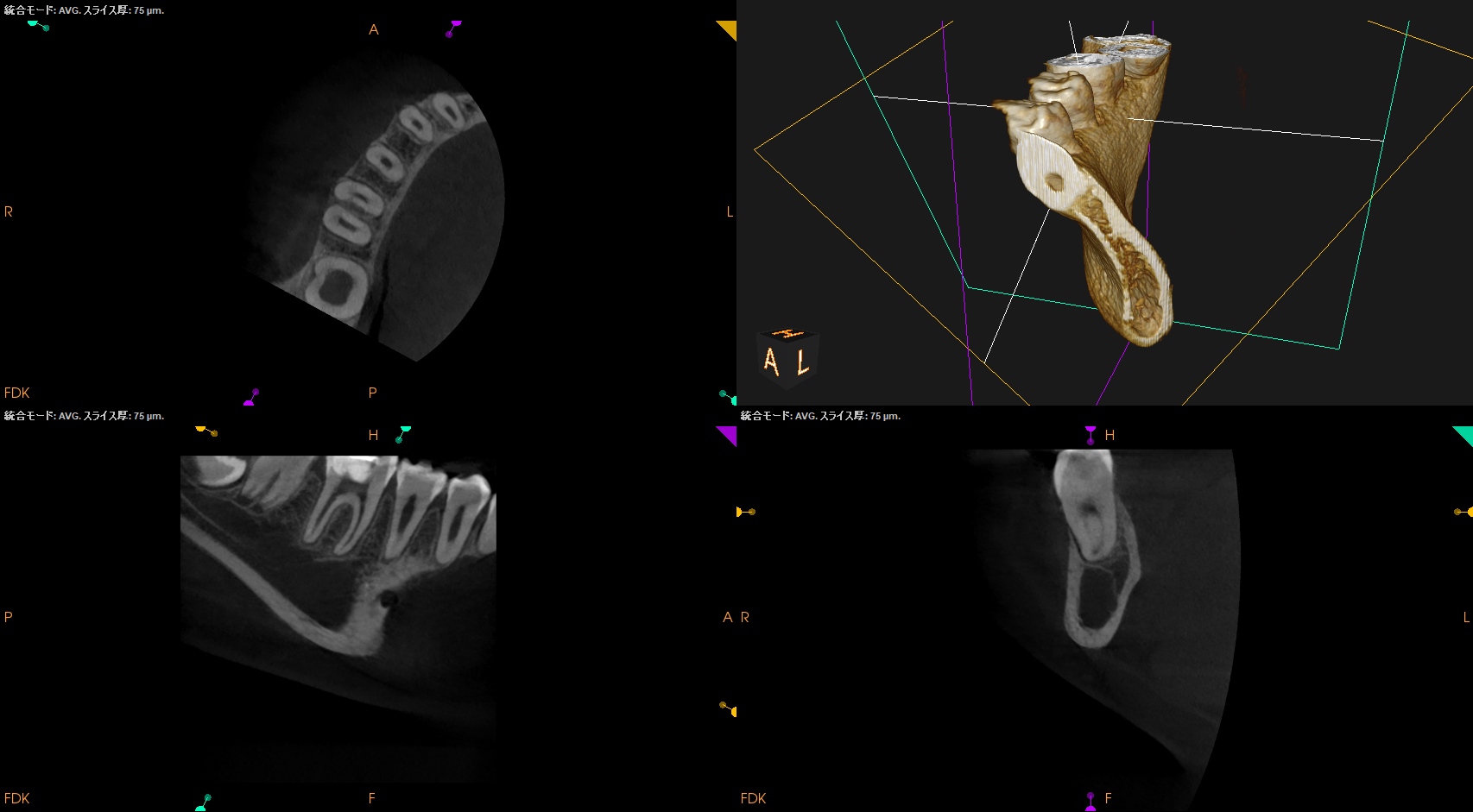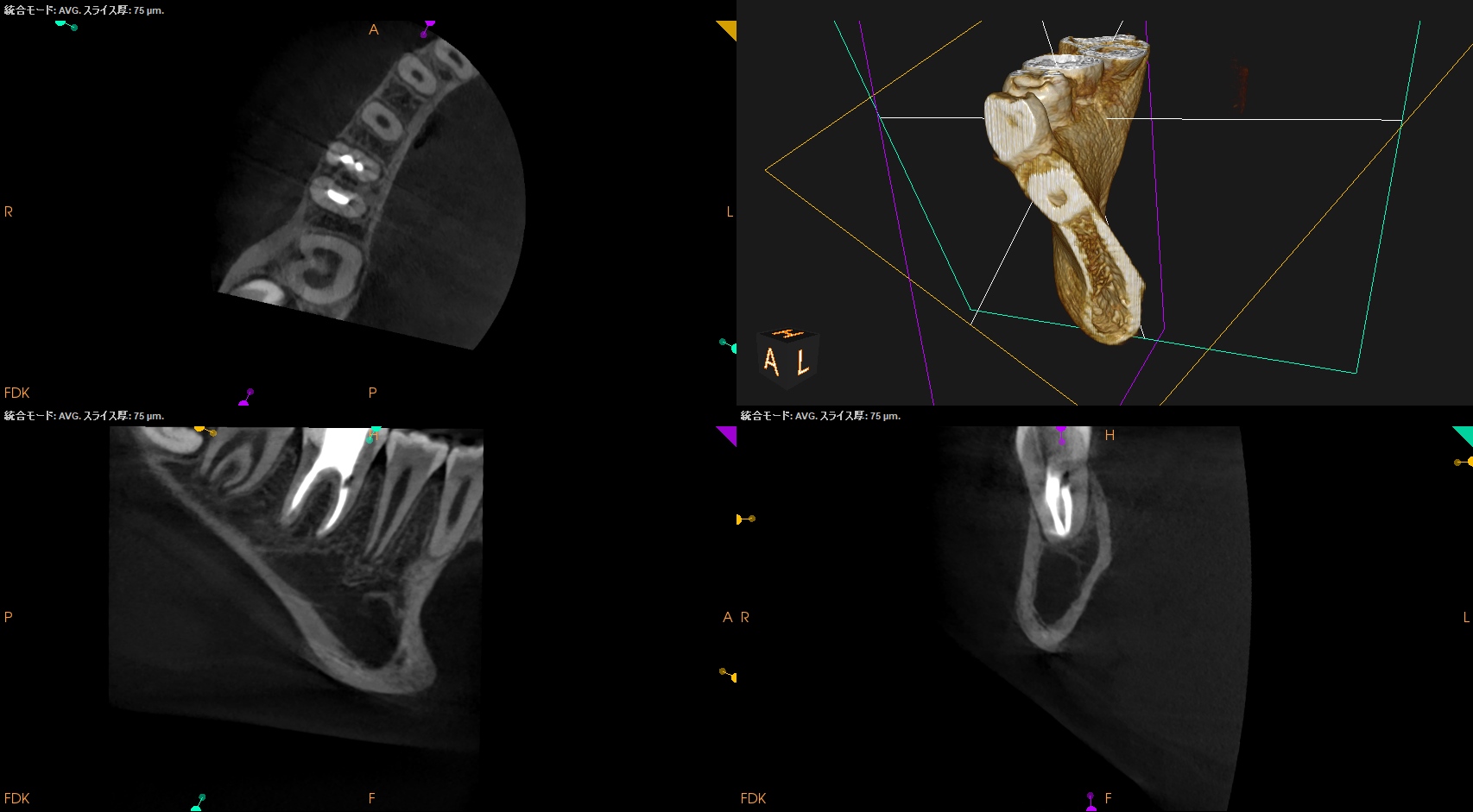紹介患者さんの治療。
主訴は、
右下奥歯が沁みる。噛んだら痛い…
である。
患者さんは中学校1年生である。
小児の根管治療を紹介先から依頼された。
歯内療法学的検査(2025.7.24)
#30 Cold+1/12, Perc.(+), Palp.(-), BT(+), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)
患歯には冷水痛、打診痛、咬合痛がある。
PA(2025.7.24)

歯髄に近い修復がなされている。
こういう治療では歯髄が保護できない。
やるなら…
症状がなければ、虫歯をわざと残して歯髄保存、
症状があれば全部断髄一択だ。
過去の治療でもその治療の正当性を示している。
ここから何がわかるか?だが、
無症状であればう蝕を残す生活歯髄療法、
症状があれば断髄一択だ。
文献的には断髄の成功率は極めて高い。
CBCT(2025.7.24)
M
MはMLよりMBの方がストレートだ。
メイン根管はMBとした。
D
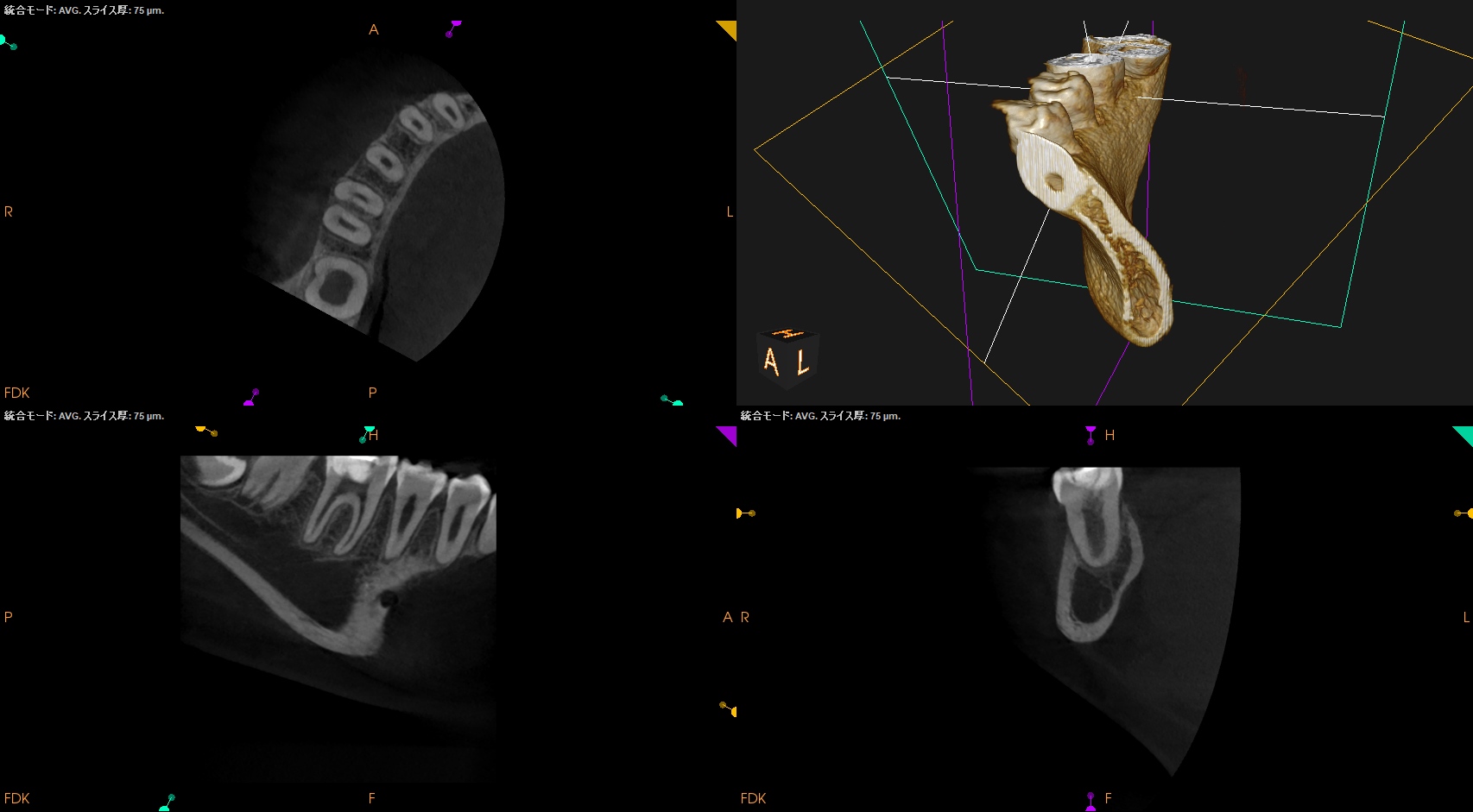
Dはかなり根管が太い。
中学1年生だからだろう。
が、病変がないのでそれほど悩む必要性もない。
歯内療法学的診断(2025.7.24)
Pulp Dx: Previously initiated therapy
Periapical Dx: Symptomatic apical periodontitis
Recommended Tx: RCT
ということで、同日治療へ移行した。
⭐︎この後、治療動画が出てきます。不快感を感じる方は視聴をSkipしてください。
#30 RCT(2025.7.24)
チャンバーオープンし、以下のように長さを計測した。
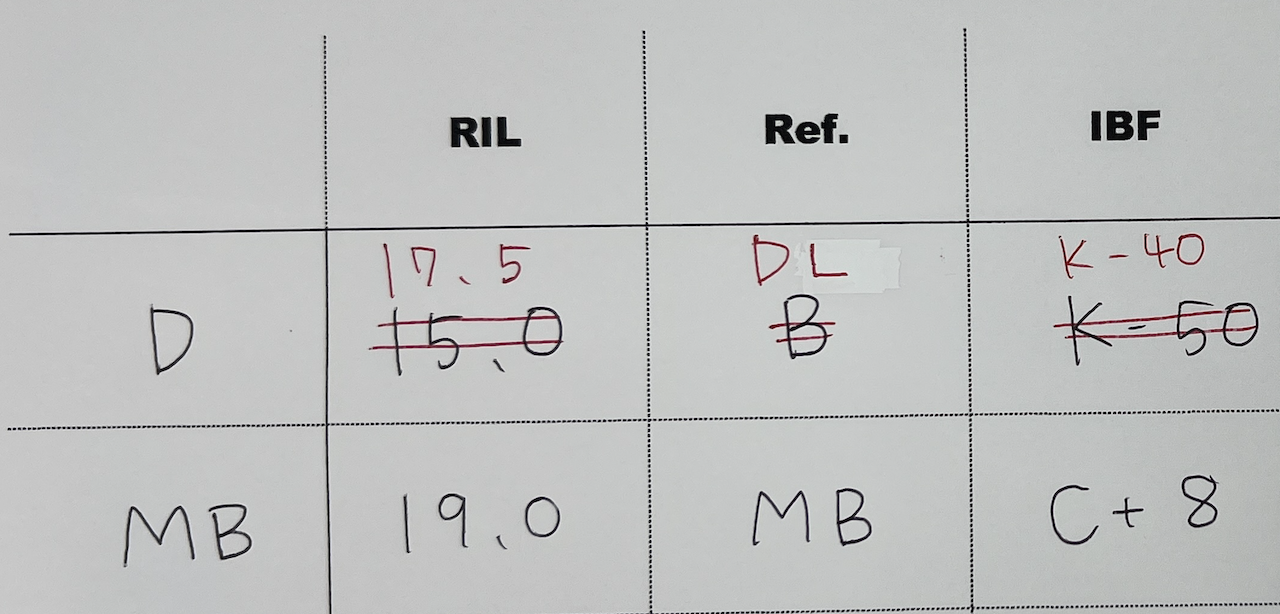
Dは#40のK Fileで穿通である。
ということは、
HyFlex EDMは事実上、#60.02しか使えないという話になる。
それで心許なければ、ProTaper Gold F5も使用すべきだろう。
MLはMBに合流するのでこの時点では長さを計測していない。
この情報からD, MBをまずは根管形成した。
さて。
上記の動画であなたは気が付いただろうか?
根管治療を患者さんに楽に行わせるには、
①治療中に痛みが出ないような麻酔を行うこと(これには知識と特別な道具が必要)
②作業と作業の間は閉口してもらうこと
が重要であると。
猿ぐつわ(開口器)を患者の口腔内に入れると、治療後に患者は顎を押さえて、治療したあなたにいいイメージを抱かない?だろう。
それが記憶に残るからだ。
なのでうちの歯科医院では上記対応をとっている。
これは臨床のコツなのかもしれない。
ここまでくればゴールは近い。
最後にMLのMBの合流部分をCheckした。
合流部分はどこだろうか?
目が見えれば…

それが18.0~18.5mmの部分であることは一目瞭然だろう。
ということは、作業長は以下のように完成する。
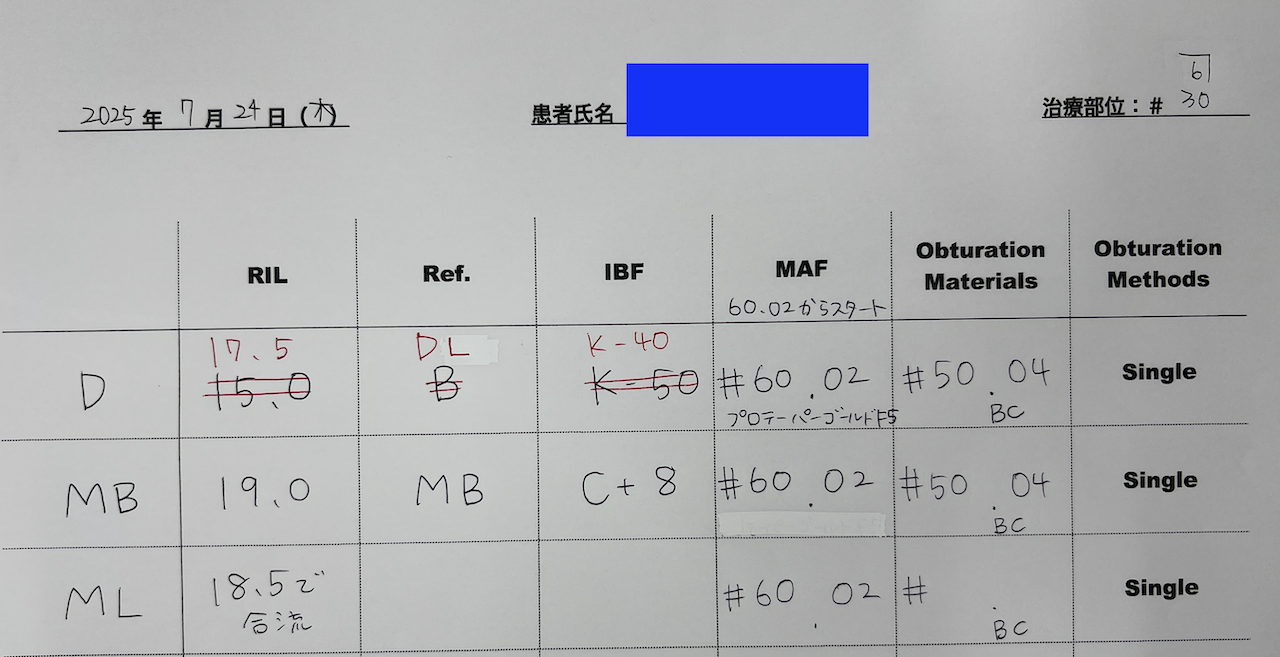
私は傷跡の先まで根管形成しているようにしている。
その方が誤差がある形成、誤差があるGutta Percha Point同士が接合しやすい気がするからだ。
あくまでこれは個人的な意見であることに注意してもらいたいが。
形成後に根管充填し、術後にPA, CBCTを撮影した。


MB
ML
D
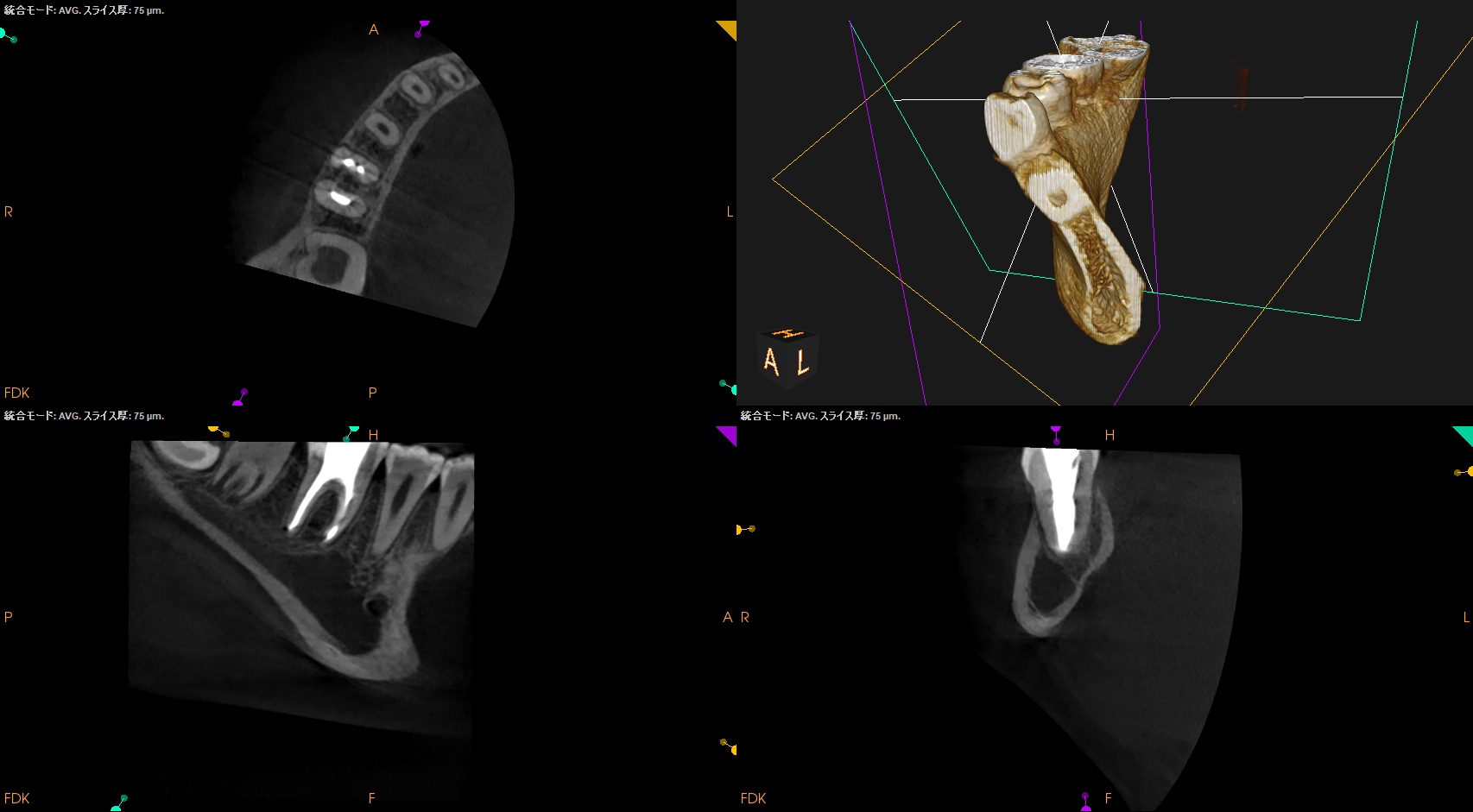
問題はないだろう。
次回は1年後である。
またその模様をお伝えしたい。